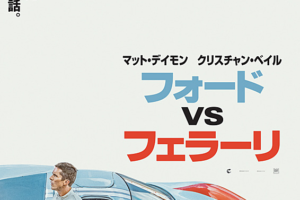アイキャッチ画像: (C)2019「君は月夜に光り輝く」製作委員会
こんにちは、ベッドカバーを換えて寝つきがちょっと良くなったワタリ(@wataridley)です。
今回は北村匠海と永野芽郁のデュエット映画『君は月夜に光り輝く』をレビューします。
今作は佐野徹夜による同名の小説(これがデビュー作だそう)を原作としており、監督は『君の膵臓をたべたい』『センセイ君主』などの月川翔。
既に評価を得ている小説を原作に、流行の俳優を登用し、前述の作品で実績のある月川翔監督がメガホンを取るという製作体制から、いかにも手堅く客を呼び込もうとする映画といった意図がみられます。また、題材も定番の「難病に罹ってしまった若者」でもあります。
簡潔に感想を述べるとするなら、やはり主演の永野芽郁と北村匠海をスクリーンで役に当てはめて眺めるプロモーション映画のようでした。原作が付いているとはいえ、今作の脚本は全体的に主演2人の関係を描くためのものになってしまっています。演出やカメラワークも同様です。故に映画としては凡庸さが否めず、なんとも記憶に残りづらい作品でした。
以降、ネタバレありの感想です。未見の方はご注意ください。
47/100

病が浮き彫りにする生への執着
発光病に罹り宣告された余命を過ぎた「余命ゼロ」の渡良瀬まみずと、姉を亡くした岡田卓也の交流がこの映画の果実である。生きたくても生きられない少女が、身近な死に触れどこか暗い感情を抱えた少年の心を解きほぐす過程が、時に暖かく、時に朴訥とカメラに映される。
渡良瀬まみずが抱える普通への憧憬
春が訪れ、学校が新学期を迎えても、渡良瀬まみずの生活は変わらず特別治療室の中に押し込まれたままだ。唯一新学期を実感できる新しいクラスメイト達からの寄せ書きにしても、義務的な匂いが染み付いている。
ただ死を待つことしかできない彼女に変化をもたらしてくれたのが、寄せ書きを持ってきてくれた岡田卓也だった。彼が初めて病室に訪れた日のちょっと距離を感じさせる会話さえも治療ばかりの彼女にとっては、嬉しいものだったのではないだろうか。
単なる形式上の挨拶で終わるはずだった2人は、卓也がメモ書きの通りにお菓子を持って再訪した時、不注意からスノードームを壊してしまったことがきっかけで親しい関係へと発展していく。
病室から離れることのできないまみずは、普通を知らない。そこで彼女は卓也に自分がしたいことを代行するよう要求する。
遊園地で遊ぶこと、パフェを食べることなど、彼女自身が出来ない体験を卓也が代行し、その感想を彼女に伝えることでまみずの生活には刺激がもたらされる。何よりも、共通の話題でコミュニケーションがとれる友達との時間は心を満たしてくれたに違いない。
最新のスマートフォンを手にしたまみずと卓也の代行は、現代的なツールの利便性を訴えかけるとともに、2人が空間を超えて擬似的にデートを繰り広げるというシーンになっている。これがとても面白く、一昔前ならまず不可能なコミュニケーションだったことだろう。(通信料は心配になるが)
一緒に家具を選んでコーディネートをするだとか、海辺をサイクリングするといった映像に宿る活力は、スマートフォン越しではありながらも、2人が心からその時間を楽しんでいることが伝わってくる。こうした時間を経ているからこそ、2人の間に恋心が芽生えていくという展開もごく自然に感じられる。病気の彼女も普通の恋愛を通じて、普通の喜びを知っていくのだ。
演じた永野芽郁は、惚けた表情がこちらを引きつける個性的な武器を持っている。「私、余命ゼロなんだ」と告げるシーンにおいて、その言葉に付随すべき重みは全く感じられず、それどころか浮遊感さえ覚えてしまう不思議な心地は永野芽郁独自のものだ。余命幾ばくもない少女とは相反したふわりとした感じが、この映画の前半部分をファンタスティックに仕上げている。それだけに、スーパームーンを観測する際の真剣な眼差しと切実な声色はそれまでの彼女と異なって感じられる。冗談を装いながら、裏では真っ直ぐに卓也へ恋情を向けている。少女らしい純真さと、素直ではないいじらしさにくすぐったくなった。

(C)2019「君は月夜に光り輝く」製作委員会
生への執着を取り戻す岡田卓也
岡田卓也はたまたま寄せ書きを届ける役を任され、まみずと知り合うことになる。不意にではあるがスノードームを破壊してしまう出来事には、まみずを閉じられた空間から解き放つ役目を彼が担っていることが早々に暗示されている。
だが、今作の物語は卓也からまみずへの一方的なアクションとはなっていない。というのも、特別治療室から出ることができないまみずと知り合い、彼女の代行をしているうちに生気のようなものが強まる様子が映像に収められているからだ。「ロミオとジュリエット」におけるジュリエット(女性)を演じる彼は、まみずの代わりの人生を生きることで、生命活力を得ているかのようだ。冒頭、まみずを前にたどたどしい口ぶりをしていた彼と違い、舞台上で堂々と振舞っている。
思えば、彼は初めのうちはあまり元気があるように見えなかった。それはおそらく恋人を発光病で亡くし、自らも死んでしまった姉の存在が頭に絡みついていたのかもしれない。死ぬ間際、姉は愛する者が死んだら後を追うことを示唆した中原中也の本の一節を読んでいた。直接的にそれが彼女の死に結びついたのか、答えを知る者は既にいない。だから卓也はそのことについて、どうしても考えてしまう
しかし、その暗い感情をどこに向けるのでもない。姉の死以来、母親とは少々摩擦が生じた仲となり、姉の死因となった車を話題に出すことを嫌う。大切な人の死から湧き上がった感情のはけ口はなかったのだ。まみずと出会うまでは。
まみずは、友人の兄と同じ発光病に罹り、毎日が退屈な時間に支配されている。そんな彼女が掲げる代行リストに付き合ううちに、卓也の心は満たされる。まみずがそうであったように、卓也もまた代行を通じて正気を得ているという関係はまさしく互恵的である。
死に瀕した存在との触れ合いが、生の喜びを見出させるという点で見ても面白い。姉が恋人の死に触れて自らも死んでしまったのとは対照的に、卓也はみるみると生きる上での動機を見つけていく。
最終的に、まみずから託された言葉が彼の支えとなり、医学生として勉学に励んでいく。この物語は、身近な者の死によって生きることへの執着が不安定となった少年が、死にゆく者の生への憧れに影響されて、立ち直る話となっている。
そこに北村匠海という役者をあてがったのは適切だ。彼のルックスは、太陽というよりかは月のようである。淡々とした表情の中に、繊細な機微を浮かび上がらせる演技が持ち味であり、その点において岡田卓也という不安定な少年に重なる部分が多い。序盤、まみず(永野芽郁)とのもどかしいやり取りの中に、死に面した人間に対する動揺とも取れるニュアンスを見え隠れさせ、その一方で後にカップ数を自然と聞き出すような男子高校生らしい面もごくさりげなく表現する。病室で彼女に寄り添う際の静かな哀しみも含めて、北村匠海は繊細な機微を描ける若手俳優に映った。

(C)2019「君は月夜に光り輝く」製作委員会
釈然としない発光病と周囲の人物
渡良瀬まみずと岡田卓也の関係性に永野芽郁と北村匠海を当て、映像面でも物語でも彼らにフォーカスする作風は、今作をどう楽しめば良いのかを明確に定めている。
とはいえ、キャストにスポットライトを浴びせるという明確な指針を除いては、今作にはあまりに不適当な部分も目立ってしまっている。
例として、自分には発光病の必然性があまり感じられなかった。今作は、発光病という架空の病を舞台装置に据えているとはいえ、生命に向き合う若者のドラマを地に足ついて描いている。わかりやすい奇跡は起こらないし、まみずと卓也の関係性も一気に発展するのではなく、交流を通じて着々と形成されていく。こうしたリアリズムの強い設計と発光病というファンタジーは食い合わせが悪く、発光病にまつわる描写の数々は不自然に浮き出ているように感じられる。
症例が少ないという説明がなされているにも関わらず、卓也の周辺に2人も患者が存在している。また、体が発行するという特殊な病気に対して取られている措置がほかの映画やドラマで見られるものとそう変わりがない。身体が光り輝くという珍しい病状だが、周囲の反応は全く描かれない。このように発行病に関してだけリアリティが感じられず、なんとも浮いている感じがしてしまうのだ。
発光病が効果的に用いられるのは月夜の下で発光して苦しみだすシーンや卓也と唇を交わし儚い命を一層輝かせる場面のみで、このシーンを除いては他の病気でも成立しそうな点もこの疑問に拍車をかける。そもそもこの2つのシーンも、前者は「苦しんで呻きだす」で代替可能であるし、後者の発光は月の光を浴びたことによるメタファーと捉えさせれば充分だ。肝心の発光演出も合成感が強く、作り手が志向していたであろうそれとは別の不気味さを覚えてしまった。
こうした不可解さは、発光病だけではない。
まみずが卓也に対して頼む代行が「親の離婚の原因を聞きに行って」という初っ端からプライバシーに触れるレベルのものであったのは、正直言って興ざめだった。何ら迷いもなく父親に聞きに行く卓也もどうなんだと思うが、及川光博演じる父親も「周囲にバレたらまずい」はずの偽装離婚の実態を卓也に明け透けに打ち明けてしまう。当日会ったばかりの、娘のクラスメイトと名乗る男子学生に。その後も娘と一緒にいるところを見たわけでもないのに、卓也を娘婿のように接待したりと理解に苦しむ言動を見せてくる。卓也に対してツンケンな態度を取っておきながら、終盤いつの間にか軟化した長谷川京子演じる母親と合わせて、全く共感できない家族像となってしまっていた。
その他にも、今田美桜演じるメイドの取ってつけたような片思い話が卓也に気づかれることなくフェードアウトしていったり、発光病に罹った親友の兄について深掘りされないままだったり、その親友もまみずに想いを寄せているのに全く卓也とまみずのドラマに関わってこないなど、単なる無駄骨に終わっている枝葉末節の描写・設定にも首を傾げるしかない。これらが卓也の心理に影響をもたらし、何かしらの形で結実したのなら、意味はあったのかもしれない。しかし、全くそうはなっていないため、上映時間を徒に引き伸ばしただけのように思える。
まとめ: 永野芽郁と北村匠海のための映画
難病ものに見られる「生への執着」に関するドラマを、病に侵されていない側にも担わせた点は斬新だったかもしれない。しかし、それを除いては、どれも既視感にあふれた映像・展開に終始してしまっている。
病気に侵された若者が恋心に儚い命を燃やすというラブストーリーははっきり言って、これまでにいくらでも作られたものであるし、そうした既往のドラマと一線を画すような面白味は最後の最後まで感じられなかった。
最終的にまみずから卓也へ生きることの後押しをするモノローグは、映画の締めとしては変に間延びしており、これまで描かれていたシーンから観客が十分に導き出せることを明確な言葉と映像で覆いかぶせてしまう。このシーンに代表される凡庸な演出と物語は、ただでさえよくある「難病もの」たる今作をそれ以上でも以下でも無い領域に押し留めてしまっている。『センセイ君主』にみられた華美な演出も題材故か鳴りを潜めている。
では、どこに着目すればよいか?それだけは明確で、永野芽郁と北村匠海の登壇と共演にこそ今作の意義は集中している。実際、流行に乗った俳優とだけあって、ルックスはもちろん、パフォーマンスにも引き寄せられた。
だが皮肉なことに、彼らがより魅力的に映る作品とは、彼らのために構築された世界などではないだろう。矛盾しているかもしれないが、俳優に左右されない創意工夫に満ちた物語に身を置かせてこそ、俳優とは真価を発揮するものだと思う。
2人が飛躍し、そうした作品の中で相見えることを今後期待する。
▼映画の原作となった小説
▼原作小説の続編