10話「夢見る笑顔」
基本1話完結の形式で進んできたKSS版『ToHeart』も、ここにきて初の前後編に。原作ゲーム未プレイかつ90年代当時の美少女ゲームの情勢を知らないため最初戸惑ったのだが、この回で初登場のマルチはどうもその界隈を大いに賑わせたアイコンだったらしい。目に見えた商業色の薄いこの作品において、特例的に2話も割り当ててもらっているあたりに、その片鱗は確かに見える。
この回から最終話までの作画監督は、前話を担当した斉藤英子とキャラデザ・総作監の千羽由利子の2名体制で担当。斉藤英子(5、9、10、11、12、13話)、千羽由利子(1、4、10、11、12、13話)とそれぞれ半数近い話数を捌いていることになる。フィルムの統制という観点では、個人的にお気に入りのアニメ『フルーツバスケット(2001年版)』のキャラデザ・総作画監督を務めた林明美(全26話のうち約半分もの回に(総)作画監督クレジット)にも同様のことを思ったことがあるが、アニメーターという人の束、キャラクターという情報の束、それらの連なりを、しかも複数の回にまたがり統制するというのは、やはり相当な労力がかかっているのだろうと思われるので、頭が上がらない。ラストスパートも息切れをまるで感じさせずに、最後まで丁寧な表情と芝居が持続している。
この前編ではメイドロボのマルチが登場し、浩之、あかりと交流を持つことになるわけだが、のっけからロボットというSF要素の投入に面食らったのが正直なところ。これまでも黒魔術が趣味の御令嬢、不幸を予知する超能力少女などといった突拍子もないキャラクター設定は出てきたが、人間と見分けのつかない自律型ロボットともなると、流石にフィクション性のレベルがぐんと跳ね上がっている。前者2名は個人とその周辺で収まるので時に不思議なこともあるもの哉と思えるが、公共空間にロボットが歩いて喋っている光景は作品世界全体とそれを見ている側の社会通念をも巻き込むのだ。
しかしそこはKSS版『ToHeart』らしく、奇異の感じを過剰に押し出しすぎない手付きで扱う。浩之がマルチの耳に対する疑問や、ロボットと聞いてから足元から頭まで眺めるチルトアップのカットにより、浩之の驚きを視聴者に同期させつつも平熱を飛び越えない温度感で描写される。メイドロボの話題に沸き立つ志保たちの会話を踏まえても、そういったものが一般に実用化され認知されているが、まだまだもの珍しい存在と捉えればいいのねとチューニングできる。ここを過剰に盛り立てすぎると、それを受け入れるか受け入れないかといった段取りが発生するので、適度な温度感での導入と言える。
このマルチはどうもロボットとしての機能よりも、見た目から感情表現に至るまで人間と見分けがつかないというコンセプトを優先されて設計されたようで、それは途中出てくるセリオなる姉妹機とも対比されて表現される。このあらすじに仕込まれている「人間らしさを獲得したロボット(ないし人工生命体)」という象徴や、あるいはそうした人間に似て非なる存在との境界線はどこにあるのかという問いそのものは、SFの分野では古典的すぎるほどであり、特段珍しい題材でもないだろう。一方で、そうした題材と美少女キャラクターと組み合わせて、人間に尽くそうとする健気さという好感を創出しようという試みは当時にしてみればおそらく斬新だったのだろうと推測できる。ロボットでありながらも人間らしい不足を抱え、自らに課せられた役目を自覚し、あまつさえその先に「死」が待ち受けているとしても全うすることを心に決めているというキャラクターは、それだけ書き出すとなかなかに壮絶であるが、そうした壮絶さを背負いながらも人間の役に立てることに笑顔を見せる様には、見ている側に憐れみを抱かせるようなギャップがあり、それが魅力として捉えられたのだろう。
じっさい、そうしたマルチの甲斐甲斐しい魅力は千羽由利子の奥ゆかしい華を持ったキャラクターデザインや、このアニメーションの織りなす表情と仕草と組合わさり、いっそうの相乗効果を上げていると思える。冒頭の時点で物を運んでいるシーンの身体のよろめきや、浩之にロボットなのに物をまともに運べないといわれた時のしゅんとした表情の変化といった細かな描写で、懸命さと不器用さが視聴者にすぐ掴ませるようになっている。劇伴とマルチの仕事の様子が流れていく場面では、セリフ抜きで状況が次々と切り替わっていく中に、ドジを踏んでしまう居た堪れなさが描かれる反面、それでもマルチ自身は懸命で充実しているような心地がシーンが連続する構成によって印象付けられる。また、セリオが出てくるシーンでは最低限の動きと表情が一定の彼女に対して、セリオが喋っている最中にもウンウンと頷いている様は、感心や同意を示すいかにも人間らしい仕草として映る。かように、あらゆるシーンで、マルチというキャラクターを伝えるための書き込みが行われている印象で挙げていくとキリがない。言ってしまえば、人気の美少女キャラクターを視聴者に紹介する性質の強い回だが、各セクション・各パートの抜かりない仕事ぶりによって、受動的に身を委ねていてもキャラクターの存在に説得力を感じられる仕上がりになっている。
個人的には、バスに乗車したマルチ達が別れの挨拶をする場面の、凝ったレイアウトや車内の透過と周囲のビルが反射するガラスの処理によって、こういう下校風景すら質感を覚えるような描き込みがなされているところに着目したい。マルチを見送る浩之達の目線を体感させ、そこに宿る光の働きを絵に拾い上げることで、作品世界への臨場感を高めており、それが見せ場ではなく、一見なんてことないような一風景として過ぎ去っていくところに光る職人技を見た気がする。
この回では、浩之が呟く「ロボットってのはセリオみたいな奴のことを言うんだよな」というラインを堺に、マルチの存在に揺らぎが与えられる。その後、彼女は誰も見てないところで犬に話しかけ、クッキーを分け与える。そして犬の気持ちを知りたいとさえ口にする。人間に尽くすロボットという役割に準ずるのであればいずれも不要な行動であるし、志保の言う通り変なのは間違いない。
一方で、ここまでマルチの動態を見てきた浩之はそうしたマルチの存在を認め、彼女の境遇を聞かされた後に掃除の手伝いを申し出る。それはここまで見てきた視聴者も多かれ少なかれ同じ心境に至っているはずだ。その感情や行動を見てきて人間と変わらないと実感しているから、浩之達は有益か否かの評価軸で見たり物として扱うのでなく、友達のように一緒に何かをしてあげたいという気になったということだ。
しかし、そんな浩之の共感を覆すように、掃除を一通り終えたマルチはバッテリーが原因で倒れ込んでしまい、図書室で充電を行うことになる。PCに接続されて眠るマルチの様子は、これまで表情豊かだったそれとは異なり、機械そのもの。浩之の言う通り「人間そっくりに見えてもやっぱりロボット」であるなら、人間にとって有益か否かで測られることは避けられない。直前のシーンで説明していたように試験期間が終わればセリオと比較され、どちらを残すのかという結論は出されることになる。そうした不穏な空気で幕を引くのはこれまでの回にはなかった特徴であり、前後編に要請される「先が気になる終わり方」を履行したとも言える。


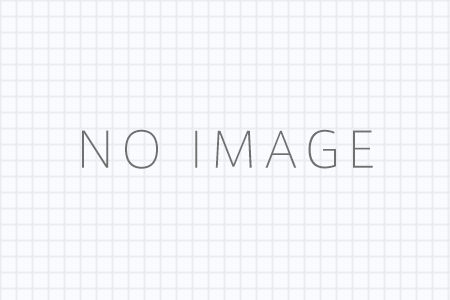





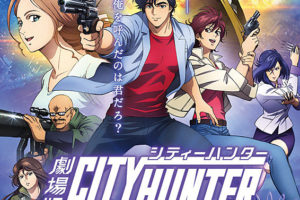





コメントを残す