11話「ぬくもりの瞳」
あかりと浩之が並木道で落ち葉を踏みながら歩いていると、ベンチに座っていた見知らぬ男から話しかけられる。枯葉は土の上では養分になるが、舗装された道の上ではゴミ扱いされる。役に立たないことは一つもないのにと愚痴でもこぼすように告げて、男は去っていく――という意味深台詞で興味を誘う導入。それから、試験期間の終わりに向けて掃除の時間でもないのに「うりゃー」と叫びながらモップがけ、購買部で人混みに揉まれていると浩之から叫んでいたパンを分けてもらうマルチの様子が描写される。前回描写されていたことを反復し、マルチが学校や浩之に馴染んでいることを冒頭で明確にしておくという前後編ならではな段取りを行なっている。
浩之は志保の「役に立つことを教えなさい」という言葉に触発されて、あかりと一緒に、メイドロボとして必要なスキルをマルチに教えようとする。家庭科室でのシーンでは、大方、アニメらしい料理下手描写が繰り広げられるのだが、大げさなギャグ表現でなく、この作品らしい落ち着いたタッチを保っている。乾麺を沸騰した鍋に入れる際の雑な入れ方(束を放射状に入れずほっぽり投げている)は明らかに普段料理をしていない手付きであるし、缶の空気穴を入れ忘れてのドタバタからカットが切り替わり、パスタの茹で時間もソースの湯煎もしくじった(よくある黒焦げや謎の物体として描画されるには至らない)リアルな失敗作が表示される。流石にここまでのドジは想定外だったのか「空気穴開けてって言ったよね?」と焦るあかりの反応が、普段のおおらかさとかけ離れておりやけに笑える。
今度はデパートに行き、研究所と学校以外の場所にマルチを連れ出すことに。久しぶりに劇伴と共にハーモニー絵の連続でその光景の一部始終を見せてくれるが、やはりこうした時間の経過やその一枚一枚のレイアウトや仕上がりでツボを外さないアニメであることを実感する。
近くで転んだ女の子を手助けするマルチ。相手を心配し、おまじないをかけるという行為はやはり単なるロボットではなく、感情を表現する人間らしい存在だからできることだと例示される。ここで浩之があかりに見守るように手で制したのは、ロボットとしての介助機能があるからというより、転んだ子を見かけて咄嗟に動き出した親切心を自分たちが介入して無碍にしないようにという計らいなのだろう。その後、浩之とあかりから服をプレゼントされると、かけられた親切にマルチは申し訳なさそうに顔を伏せる。先ほどは女の子を励ましていたマルチだったが、実のところメイドロボとして事あるごとに失敗続きだった自らの不甲斐なさを感じており、浩之とあかりからのここまでの料理の練習やプレゼントは彼女を励ますためのものだったというわけだ。
Bパートでは、マルチの学校最後の日を2分近く台詞もなしにじっくりと映す。教室、下駄箱、階段、廊下といったそれ自体なんてことのない光景が、特別なニュアンスを帯びる。ここでかねてから丁寧に描いてきた校内の温かみのある背景美術だとか、窓越しに校内に聞こえてくる運動部の掛け声、鳥のさえずり、吹奏楽の演奏といった細やかな音の演出が存分に効果を発揮しているから、マルチが肌身に受けてその内側で起こっているであろう感傷を、見ているこちらも想像できるかのような心地になれる。台詞を排してシンプルな景色と被写体の所作に留めたこの2分近くは贅沢な空白のようであり、ここまで『ToHeart』が力を入れてきた校内に宿る息吹への自信が窺えるようでもある。そして、マルチが去った後には、今度は浩之視点で日常風景(購買部や廊下の掃除)が反復されることになり、そこではいつも通りの校内がまた異なった視点からのさみしさを伴って感じられる。
浩之達は帰路につこうとしていたマルチに卒業証書を送る。ロボットであることを忘れたかのように、最後まで学校を去る友人のように応対するというのは、一見粋なはからいに映るが、マルチと交流して自然と湧き出た――単純にそうしたくなったという――行動でもあるのだろう。あかりがメイドロボは望まないがマルチみたいな子となら一緒にいたいと答えるのも、根底では同じことのはずだ。
その後、冒頭と同じ場所のベンチに腰掛けていた例の男と再会することになるわけだが、原作のゲームをプレイしていなくとも登場したタイミングが出来すぎていることから、この人物がマルチの関係者であるということは察しがつく(クレジットでは長瀬と名前が表記)。結局彼は劇中で素性を明かさず、さらには会話も体裁上はマルチのことを伏せて行われる。結果として、マルチを主役とした回のクライマックスながら、その枠組みを少し拡大して、冒頭で言及された役に立たないとされるもの=人間らしさを伴う他の存在にも敷衍した問いかけにもなっているというのが、少し洒落ている。
ここで彼らは、人とそうでないものとの違いについて話し合う。この人物は人間だってあらゆる作為・無作為的な要因によって作られたものであり、人為的に作られた機械との差異も本質的には存在しないのではないか、あるいは反対にプログラムに基づいて行動するしかない機械はどこまでいっても人間になれないのかといった問いを投げかける。これは前回の感想でも述べたことだが、これ自体は既往のSF作品で同様の主張を含んでいるものを探すのにそれほど苦労しないだろう。ただ、これに対する浩之の「一緒に泣いて笑って喜びあえる仲間ならそれでいいと思う」と、はっきりと現実主義に根ざした回答を口にさせて、マルチという存在をなぜ登場させたのか(劇中の言い方ならば、なぜ開発したのか)ということを総括させている。ここは、この作品らしいウェットになりすぎない適当な温度感を保った美点として受け取れる。
というのも、マルチというキャラクターを安易に魅力的に描こうとすると、マルチという機体が特別愛らしく、そして本当に人間の心を思いやってくれるような奇跡的な存在であるというやや都合の良い理想像を導くきらいが考えられる。しかし、浩之と長瀬が交わした会話は、マルチにまつわる会話であることを伏せているためにマルチという個体に限定された議論ではなく、更に機械が果たして自分たちと本当に心を通わせられるのか否かという真偽性は留保した上で、他の誰でもない自分が一緒にいたいと思える相手ならばどんな存在だろうと必要なのだという究極の結論に達するのだ。例としてここでは鳩が挙がっていたが、要するにペットの動物とそれを飼う人間同士が本当に心を通わせているのかという証明は不可能であっても、人間の側が必要だと感じるのなら一緒にいるという、ただそれだけの、そうとしかいいようのない現実に即した結論である。そしてこれは拡大すれば、人間同士でも同じことが言えるはずだ。
メイドロボがまた学校にやってくると聞いても浮かない顔をしていたように、短いながらマルチとの時間を共に過ごした浩之にとっては、マルチは他の機体とは異なる存在に感じられるようになっていた。上記のようなリアリストな考え方を根底に敷いた上で、それでもなお浩之達が相手の不在をさみしく思っているという最後の様子に、冷静な視点とキャラクターの主観的な感情の中庸をいくような今作らしい温度感が見出だせる。そんな浩之達の感傷を遮るように、やってきたメイドロボがあのマルチだったと発覚して彼女の笑顔で締めくくられることになるのも、同様にウェットになりかけたところを朗らかに振り戻すようなオチである。それと同時に、おそらくは、浩之との会話を受けた長瀬によるなんらかの働きかけにより「落第」と称してマルチは戻って来ることになったのだろうという推測も自然と成り立つ。
言ってしまえば人気キャラで前後編を使った話だったわけだが、大枠で見れば困っているゲストキャラクターを浩之が表立って助け、あかりがその様子を見守るという構図はこれまで複数あったパターン(3、4、6話)と共通しており、それらのクライマックス前の拡大版という位置づけだったことが読み取れる。もっともマルチはロボットという存在の特異性もあってか、あかりがそのキャラクターと交流する浩之に対して不安や安堵を抱く予感の描写すら今回は皆無で、前後編通して息ぴったりの二人になっている。次回は引き続き前後編でいよいよ物語の最後を飾ることになり、そこであかり達に起こる出来事を引き立てるため、直前の回はあえて彼女らの関係は通常運転にしたのかもしれない。
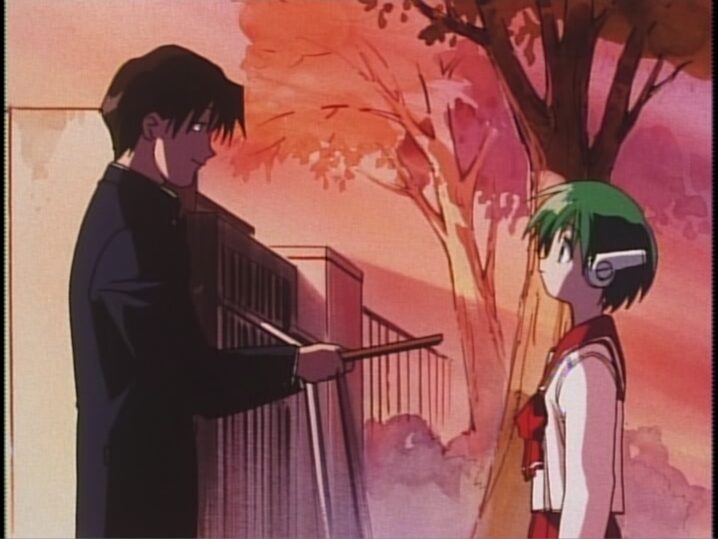


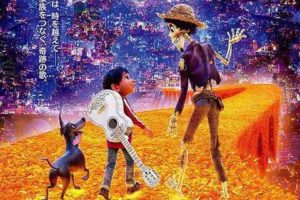
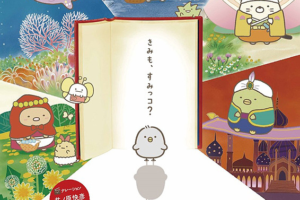









コメントを残す