アイキャッチ画像: (C)2019「HELLO WORLD」製作委員会
こんにちは、最近やっと毎月美容室に通うようになったワタリ(@wataridley)です。
今回は伊藤智彦監督によるアニメーション映画『HELLO WORLD』の感想を書いていきます。
『HELLO WORLD』のそのビジュアルと設定から、期待値を高く持って鑑賞に臨みました。
自分たちの世界がただのデータであるという事実を告げて始まる予告編には、若干のぎこちなさを感じつつも、ジャパニメーションでよく見る大きい瞳のキャラクターが3DCGで描画されていて、彼らの青春とピンチの時がOfficial髭男dismらのキャッチーな曲で彩られています。既往のアニメーション作品からはみ出たセンスを見て、これは面白そうだと思っていました。
また、キャスト陣にも注目せざるをえません。『君の膵臓をたべたい』で共演し、今や揃って若手俳優の期待の星たる北村匠海と浜辺美波がメインキャストを務め、キャリアを積んできた松坂桃李が彼らを見守る役所で出ているというのですから。
自分は見たことがないですが、大人気アニメ『ソードアートオンライン』シリーズを代表作に持つ伊藤智彦監督が手がけるとのことで、その点も期待要素のひとつでした。
作品の簡単な感想を述べておくと、SFの浪漫を多分に含んだストーリーの中で、1人の少年の成長と恋する女性との交流、意欲のあるデジタル表現、データ世界の危機を救う中で導き出されるメタフィクショナルなメッセージなど、大好物な素材が目白押しでした。とはいえ、そうした大量の洪水を浴びせられた気分故に、ひとつひとつにもっと入り浸りたかったという気持ちもあります。
以降、ネタバレを含む感想を書いていきます。未見の方はご注意ください。
66/100

目次
日本のアニメらしいテイストを敢えて取り入れた3DCG
この作品では、堅書直実らキャラクターと背景はすべて3DCGで描画される。
しかし、少なからずリアリズムを取り入れた表現を志向する従来の3DCGアニメーションとは異なり、今作のキャラクターはデフォルメ化されたアニメのデザインを流用している。『らき☆すた』『けいおん!』などで知られる堀口悠紀子がキャラクターデザインを務めている。丸めの大きな瞳や細い眉といった、どちらかというと少女漫画寄りに思える繊細な造形は、ファンの多い上記の作品でもお馴染みだ。
通常の3DCGで拘りそうな肌の質感や細かな毛束の動きといったものより、シンプルな顔文字のような表情でわかりやすく登場人物の性質や機微を伝えようとしている。堅書直実の下がり気味の眉とタレ目を見れば、強くものを言えそうなタイプではないなと判別できるし、それと比較してカタガキナオミ(先生)はより大人びた印象を与えるシルエットと目つきをしているので、「10年後からきた」という情報が外見にきちんと表れている。一行瑠璃の一見近寄りがたいツリ目と硬い表情からもキャラクター性が如実に読み取れるし、それが接近と共に柔らかくなるというのもベタだが、ベタなりに掴みやすい。これらは、アニメではふつうの表現技法なのかもしれないが、3DCGに持ち込んだ上で、アニメチックなキャラクターの性質を再現しているところが斬新である。
平面の絵に比べて、立体のキャラクターは、再現度の高い京都の街並みにも馴染んでいる。一方で、3DCGの多用が、直実の住む世界がデジタルで彼らがその一部だということに、一種の説得力を与えている。写実性を演出しつつも、これが機械の中で起こっている架空の出来事だという舞台に仕立て上げているというわけだ。3DCGを採用したことで、作品世界を補強していることには感心した。実際、最後の最後には、従来の手描きのアニメになっていて、視覚的にそれまでの世界とは別の次元にあることが示唆されている。
第二幕以降で描かれる混沌とした世界の危機も今までにない表現を目指しているかのようだ。虹色の柱が隆起することで告げられるグッドデザインの発動は鮮やかで見栄えがいいし、思い描いたものが次々と具現化されていく怪奇な光景を見ていると、快感を覚える。を整然とした京都の街並みが折り畳まれゆく様子は『インセプション』を彷彿とさせるが、場所は日本の古都だというのだから、デジタルと歴史が折り重なった悪夢には独特の趣がある。2037年にダイヴするシーンでは、周囲では流動体がうねり、直実は凄まじい速度で移動し、眩しい色の洪水を突き進んでいく。情報が頭で処理されるより前に次の情報がどんどん雪崩れ込んでくるのは、混乱するが、その混乱自体がアトラクションと化していたように思う。辿り着いた先のお寺にしても、落ち着いた木造りの建物が圧倒的にそれを取り囲んだ異様な空間と不釣り合いで、頭にこびりついて離れない。後半は、過剰供給とも言えるぐらいインパクトを与えまくってくるが、見ているこっちの目は退屈することがないので、映像作品としては非常に力が入っていることは間違いない。
3DCGについては、正直ちょっとぎこちなさを感じるシーンはあるものの、立体化しても相変わらずアニメーションらしい豊かな表情とダイナミックな動きを実現している。近い将来、日本の3DCGは『STAND BY ME ドラえもん』等の制作会社の白組のようなリアリティを取り入れたタイプとは別に、今作のような流派も一角をなすのではないかと思う。
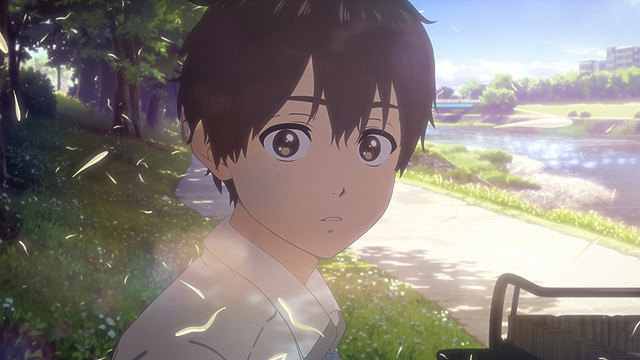
(C)2019「HELLO WORLD」製作委員会
声でみごとな個性付けをしたキャスト
データ世界と愛する者の存亡をめぐって奔走する登場人物たちに声をあてた北村匠海、浜辺美波、松坂桃李のメインキャスト3人の立ち回りにも大いに満足することができた。
北村匠海は、『君の膵臓をたべたい』『君は月夜に光り輝く』などにも共通した、無垢な少年という役所が非常にマッチしている。今作の堅書直実は、当初は信号が切り替わる直前の横断歩道を渡ることを躊躇するような自己主張のなさが目立っているが、愛する人を救う為に意思を確立する中で徐々に逞しさを身につけていく変化の過程がある。それを北村匠海は、軸となる澄んだ少年の声は一定に保ったまま、徐々に軸足を安定させていくかのような形で暗に表現してくれる。後半は大声をあげるシーンが多いが、先生を守る時の「嫌だ」という必死の叫びの中に、子供っぽい駄々にも聞こえる未熟さが微かに忍ばせられており、故に純粋なる少年の心の叫びとなっている。
一行瑠璃を演じた浜辺美波の声は、意外にも、とても刺々しい印象だった。声だけを切り取ると、透明感のあるルックスとは裏腹にこうもハスキーな声をしていることに気付かされた。彼女のハキハキとした喋り方と合わさって、「生真面目な図書委員」というキャラクターが自然に構築されていたように思う。物語の中ではあまり彼女の人物像は深掘りされないのだけれど、河原でのシーンにおける好きな小説の語り合いなどでは、とても心地よい淑やかなお芝居に切り替わっている。このギャップを見せるシーンで、一行瑠璃を助けたいという直実と観客の目線が同じになる。まだまだ成長の余地は感じさせるが、『となりの怪物くん』なども見ていると、彼女は、主演だけじゃなく、限られた情報の中でキャラクターを演出する力も確実にある。
そして、松坂桃李だが、これが抜群に良い。彼の深みのある声が吹き込まれたことによって、カタガキナオミが辿ってきた苦境が言外に感じ取れる。登場したての序盤においては、割と世界観の説明を任されているキャラクターなので、いわゆる説明台詞は多い。しかし、淡々と喋っている中でも、きちんと調べには波が感じ取れるので、あまり退屈さを感じない。専門用語を交えた台詞の慣れた調子にしても、彼は大学の研究員だという役所にマッチしている。中盤までは良き指導者らしい頼もしさを発揮し、一行瑠璃を連れ去った後は冷酷で無機質な声色に落ちていく変貌ぶりも切ない。公式サイトによると、伊藤智彦監督は『パディントン』の吹き替えで彼の起用を決めたというらしいが、あの英国紳士クマとは全くベクトルの異なるキャラクターである。悲しみを抱えたキャラクターに、持ち前の表現力で血を通わせるあたり、やはり彼は日本映画における逸材と言わざるを得ない。
今作は、この手のアニメ大作映画でよくある、「著名なキャストをメインに据えて、脇を声の仕事で実績のあるキャストで固める」という布陣になっている。ノリの軽い大学教授は童顔の中年男性という変なデザインなのは気になったが、子安武人もそれに合わせてコミカルな声色を徹底していて、流石の技術である。福原遥も作品世界に溶け込んでいたが、キャラクター自体には不満はあるので、詳しくは後述。
まとめて、キャストのパフォーマンスは見応え抜群。本来はただの絵で、まるっきり嘘のはずのキャラクターが息づいて見えるのは、彼らの魔法の成果である。
タイトル「HELLO WORLD」がもつ意味
今作ではプログラミングの入門編において、頻繁にみる「HELLO WORLD」を作品のタイトルとしている。これについて、どんな意味を持つのかを振り返る。
現実の延長線上にある空想への信頼
「実は自分たちの世界が作り物だった」というのは、昨今ではさほど珍しいものでもなくなったが、今作ではあっさりと序盤で明かし、以後それを前提として物語が進んでいく。『マトリックス』を思わせる筋書きだ。
10年後の未来である現実世界からやってきたというカタガキナオミは、最初はこのアルタラの世界で一行瑠璃が悲劇を回避し、過去の自分と幸わせに暮らす光景を実現したいと語り、直実に協力を要請する。過去を改竄したところで、未来が変わるわけでもないのだが、それでも彼は現実に叶わなかったことが仮想の上でも叶うことを望む。彼の姿は、現実の問題に頭を悩ませ、フィクションに幸福を追い求める我々観客と知らず知らずのうちに重なる。後に嘘であったと明らかにはなるが、この共感のおかげでナオミの行動を応援したくなる。
「最強マニュアル」なるものを元に未来に起こる出来事と、更にはグッドデザインの使い方を直実に教える過程は、現実世界の観客がフィクションの住人に直接干渉して、軌道修正を図るかのようで、他人事とは思えない。その歴史の改竄によってデータの世界では修復機能が働き、瑠璃はピンチに陥るが、ナオミが直実に伝授したグッドデザインによって悲劇を回避することができた。
三本足を持つ八咫烏が変身したグッドデザインは、想像が持つ力を形にしたものだろう。ナオミが侵入してきた2027年の世界は彼にとってのフィクションであり、その中では具体的な想像を行えれば何でも自由自在に具現化することができるというわけだ。と言っても、ナオミ自身は権限がない(=物語に介入できない)ため、その力の行使はあくまで物語の登場人物である直実に委ねられる。『HELLO WORLD』という作品は、ナオミがデータ世界に介入してきたことと、グッドデザインの存在を見ていると、暗に空想の在り方をテーマにしているこが察せられる。
加えて、河原にて直実が瑠璃に語るある言葉が、このテーマを浮き彫りにしている。「SF小説は現実の延長線上にある」という台詞は、直実の視点では空想を思い描くことへの信頼があり、彼が最終的にグッドデザインを使いこなすことができる布石として機能している。我々の視点からだと、今作を含めたあらゆるフィクションが現実と何かしらの形で繋がっていることへの言及になる。

(C)2019「HELLO WORLD」製作委員会
直実というフィクションが、ナオミという現実を変える
そして、ここでの「自分は脇役だけど」という謙遜の言葉は、自分よりも他者を優先する直実の性格を言い得ている。
物語の中盤において、ナオミは瑠璃を奪い去って、現実世界(と彼が思っていた世界)の瑠璃の意識を目覚めさせる。ここでの彼は目的のためなら何を犠牲にしても構わないという思考に囚われてしまっている。もう「自分は脇役」と言っていたかつての彼はいない。瑠璃が彼のこと「堅書さんじゃない」と拒んだ理由には、自己中心的な行いが彼を別人に変えてしまったというニュアンスがある。
一方で、直実は絶望的な状況の中で、そうするしかなかったという事情もあるが、瑠璃を助けたい一心でデータの世界を踏み越えて彼女の元にやってくる。かつての直実は彼女を元の世界に帰すため、グッドデザインを行使して必死になって街を走る。そんな彼の姿勢を放って置けなかったナオミは彼らの逃走を手助けする。
愛するがあまりに身勝手な行いで瑠璃を奪い去ったナオミに対して、しかし彼女は彼の持つ自分への愛情を認めて抱擁する。「君が好きだったんだ」という台詞も、これまでの経緯を見ていると、空想へ強い憧れを持った人の言葉のように耳に響いてくる。つまるところ、この映画は、SFに代表される空想の産物が現実に何かしらの形で恩恵をもたらす光景を描いているのではないか。この時、ナオミは「自分は脇役で、主役はあいつだ」と自分の身を引き、他人の幸福を願うかつての姿を取り戻す。このシーンは俯瞰してみると、直実というフィクションからナオミという現実が影響を受けて変化するシーンにも解釈できる。
振り返ってみると、古本市に関する話はこのクライマックスへの重大な布石になっていた。必要な過程だからという理由で冷酷にも火事を黙って見過ごしたナオミは、そのことを直実に咎められ、2人は一度は対立する。瑠璃の悲しみを見過ごせなかった直実は、真夜中に修復作業を試みる。直実とナオミの対照性がここに如実に表れている。しかし、その奮闘にナオミは心を動かされ、最終的に協力する。彼らの違いと、共通する優しさが見出せるシークエンスだったと思う。
最終的に千古教授がアルタラ装置のスイッチを押したことで、「開闢」が起こり、2027年の京都は全くの別世界になった。これまで辿ってきた出来事は作り物に過ぎないものである。しかし、現実に干渉するほどの影響力を持ったそれらは、もう作り物の範疇を越えて、ひとつの世界を形成するのではないか。この結末にはそんな絶大な浪漫が込めらているように思えてならない。「HELLO WORLD」はそうした想像の世界が動き出す第一歩なのだ。

(C)2019「HELLO WORLD」製作委員会
ラストでひっくり返されたセカイ構造
予告編においても匂わせられていた「ラスト1秒でひっくり返るセカイ」であるが、実際に見たところでも大きな驚きがある。
新天地に立った直実と瑠璃を映してのタイトル表示の後、画面が映し出したのはもっと未来の月面に造られた施設。目が覚めたナオミに「やってやりました」と告げる女性は、一行瑠璃。この映画は、最後の最後に更に外側の世界があったことを提示して幕を閉じる。
物語の途中では、病室にいたナオミが修復プログラムを見て、この世界も作り物であることを初めて自覚する。つまり、2027年の直実は2037年のアルタラ世界の中にいたということであり、物語は三重構造を取っている。
物語は瑠璃を救うためという目的が一貫していたが、これさえも実は違っていた。真の現実で眠っていたのは、ナオミの方であり、この物語は彼の思考を「身を呈して瑠璃を救おうとした時」に近づけて同調させることで意識回復をさせるためのものだったのである。
当初は「瑠璃が死亡した」と語られるも、後に「瑠璃は死んだのではなく脳死した」と覆される落雷事故は、実は「ナオミが瑠璃を庇って脳死した」というのが真相だと導き出される。
作中では、瑠璃を目覚めさせる目的のために利己的な思考に囚われてしまったナオミは、
最終的に直実の純粋な心に感化され、自己犠牲の精神を取り戻す。そうすることで、ようやく彼は目覚めることができたというわけだ。
直実が2037年に移動する際に出会ったあの八咫烏は、現実世界の瑠璃が送り込んだアバターだと考えられる。ナオミの意識を取り戻すために直実に協力した、つまりはナオミが2027年でやったことと同じことを2037年でやっていたことになる。
ちなみに、八咫烏の声を釘宮理恵が務めていて、瑠璃役の浜辺美波と異なっているのは、同じ声にすると観客に早々にバレてしまうことを制作上考慮したものなのかもしれない。作中で説明をつけるのであれば、序盤にナオミの口からアバターは自由に姿形を設定できるという説明があったので、声も自由に選べたということなのだろう。
『HELLO WORLD』○○○○○○○○○○の声を変えているのは、○○○○○○○○○○○○○○○○『レディ・プレイヤー1』の吹き替えの山寺宏一のアレみたいにならないように。 https://t.co/LtXhcITH7W
— ワタリドリ(wataridley) (@wataridley) September 23, 2019
デジャヴの過剰供給
物語はSFのデータ世界を舞台に一行瑠璃をめぐる恋愛ドラマがある。色々な要素を取り入れてはいるが、話の骨子自体はとてもシンプルで、直実とナオミの行動はすべて好きな人と結ばれるためのものだ。
とはいえ、それは物語の最後に覆される。そもそも物語の内実は女性をめぐる男性の闘争なんかではなく、女性が男性を救おうとしていたという事実をもって締めくくられる。日本におけるトロフィーヒロインに対するアンチテーゼとも取れて、試み自体は痛快だ。
ただ、そうしたせっかくのシンプルな筋書きと、シンプルなどんでん返しが、思いの外初見ではすっきりと入ってこない。今作には装飾物があまりに多い。ツリーを豪奢に飾り付けたはいいものの、お陰で木の幹や葉が見えにくくなっている。
2027年における直実の青春について言うと、今作の冒頭では自己啓発本通りに動けない様子を描写し、あたかも彼の成長を描く物語かのような印象を植えつけてくる。
しかしその割には、ここがデータ世界に過ぎないという事実を筆頭にした奇想天外なSF要素・世界観の説明がしばらく続き、彼自身の精神面での成長描写にスポットライトが当たることはない。更に、ここへグッドデザインの修行パートや、図書委員たちの青春映画的な要素が参入してくることで、散漫とした印象を与えてくる。勘解由小路など、意味ありげに配置していたにも関わらず、意図が不明のまま終わっている要素もある始末だ。
古本市のエピソードを除いては、直実の悩みや決断といったものが密に描かれずじまいのまま、物語は中盤、終盤へと突入する。その頃になると、もう直実自身の話というより世界の存亡や混乱というスケールのデカイ話にすり替わっている。前半ではほとんどスポットの当たっていなかった大学研究員たちの話まで出てきて、物語を積み上げた上でのクライマックスらしいカタルシスが感じられない。なんだか、ショートムービーを連続で見せられているような感覚だ。前半の青春劇は後半の都市崩壊といまいちリンクしているようには見えないし、前半で信号点滅状態の踏切すら渡れなかった直実が巨大な怪物に立ち向かうための段階を踏んでいるようにも思えない。
このように、さまざまな要素を詰め込んだはいいものの、それぞれが今ひとつ飛び抜けない。ひとつひとつ分解してみると、たしかに興味惹かれる要素ばかりなのだが、それが100分弱という物語の中で有機的な結びつきを持たず、まばらなまま点在してしまっている。それぞれの繋がりは辛うじて存在しているように見えるが、いかんせん情報量も多く、上映時間内で整理しきるのは至難の業だろう。
これらが原因となって、特に不満として上がってくるのが、ロジックが飛躍したオチの部分だ。アルタラ装置のあのスイッチについて、事前では特に説明がみられないので、千古教授の口からビッグバンだの開闢だのと言われても頭が追いつくはずもない。最終的に生じたとされる新たな次元についても、不鮮明な部分が多いために、あの世界に立った直実と瑠璃をどういう気持ちで見ればよいのか、気持ちが迷子になる。そして最後の大どんでん返しである。新たな次元に旅立ったと言う彼らでさえ、やはりデータ内での出来事なのか?という新たな疑問が生じたりして、物語の基本的な解釈すらできずに話が終了する。
今作は先に触れたように『マトリックス』『インセプション』などといった大作SF映画の影響を隠すまでもなく匂わせまくっている。そして、2016年にヒットした『君の名は。』ライクな音楽パート、日本のアニメではポピュラーな学園要素、異世界からやってきた存在から渡された能力で戦うバトル要素など、挙げたらキリがないくらいに、デジャヴを感じる要素がビッシリ敷き詰められている。しかし、上映時間の都合もあるのか、それらはどれも出番を終えるとあっさり流れていく。
例えば、劇中歌の使い方もやけにおとなしい。予告編であれだけ魅力的に聞こえるOfficial髭男dismの「イエスタデイ」が流れる場面では、リズミカルにカットをつなぐとか、歌詞とシンクロする状況を作ってMVらしい遊びを入れるといった形で作り手の拘りが見えてこない。ただ、文通を交わす様子を順繰りに映したりするだけ。模倣元と思われる『君の名は。』などに比べると、凡庸なやり方になってしまっている。
「デジタルの古都で創世記を再演する少年少女」といったせっかく斬新なアイデアがあるのに、こうしたデジャヴの洪水で話の筋道が散漫になっているので、結果として何がしたかったのかよくわからないという印象を持たれかねない。100分に満たない尺の中で、あれだけSFの設定を陳列しているだけでも無理がある。そんな中で、デジャヴを感じるジャンルを大量に並べられたら、尚更何に着眼すればよいのかわからなくなるというものだ。

(C)2019「HELLO WORLD」製作委員会
まとめ: アトラクティブな映像と物語の中から掴みとれたのはほんの一握り
映像面では手描きのアニメーションらしい外見の3DCGを使ってキャラクターの表情をわかりやすく伝えており、グッドデザインを用いた奔放なバトルやデジタル世界であるが故の無茶苦茶な現象で目を楽しませてくれる。奇想天外な映像を大画面で観られたというだけでも、満足度は高まるものだ。
ただ、述べてきたように話は筋を覆い隠してしまうぐらい多くの要素が入り乱れていて、中には明らかに不要だと感じられるものまであったりする。せっかくテンションを上げてくれるはずの音楽もBGMと化していて、惜しい気持ちになってくる。
最後のオチの部分でセカイをひっくり返されても、前段階での積み上げが強固でないがために、土台からぐらついている印象さえ受けてしまうのも勿体ない。明らかに100分弱の尺に悩まされているのを見るに、もっとスリムにするべきだったのではないかと率直に思う。この脚本は、海外の大作映画級の尺があっても足りるかどうかわからない。
とはいえ、現実とその延長線上にあるSFの関係を思わせるナオミと直実の関係の映し方は面白い手法だと思う。単なるタイムスリップではない、作り物の世界の自分との邂逅には浪漫がある。また、空想の世界を大げさにも思えるくらい持ち上げる「HELLO WORLD」というオチも、そこに至るロジックを納得できるように組み立てていたら、清々しく思えたかもしれない。
やりたかったであろうことはとても面白い。しかし、混沌としたこの作品からは一握りしか掴み取ることができないもどかしさがあった。
関連記事: フィクション世界に生きる者たちを描いたアニメ
▼設定面では非常に通うところがある『SSSS.GRIDMAN』
▼大人気RPGをプレイしているかのような感覚こそ作品の仕掛け『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』
▼雨雲がかかった現実を前に、己の進がままに生きてみせよと言い放つ『天気の子』

















