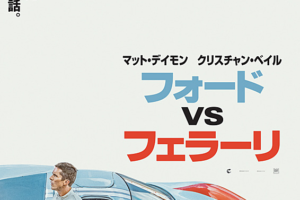アイキャッチ画像: (C)河野裕/新潮社 (C)2019 映画「いなくなれ、群青」製作委員会
こんにちは、映画『ジョーカー』の予告編をヘビーローテーションするワタリ(@wataridley)です。
今回は河野裕による同名小説の実写映画化『いなくなれ、群青』をレビューします。
監督は柳明菜。主演は横浜流星と飯豊まりえ。どちらも若くして注目を集める新鋭のクリエイターとアクターですね。
さて、この自分自身はこの原作小説を全く読んでおらず、この作品が「階段島シリーズ」という一連の流れの中にあることもわからないまま映画館に鑑賞しに行きました。
そう、主たる鑑賞動機は横浜流星ですね。彼の刺すようなシャープな目つき、しかしそれでいて憂いを感じさせる繊細な瞳、フッとした笑いを浮かべた際の柔らかな印象など、どれをとってもチャーミングです。これはもう観ないわけにはいきませんでした。
他に並ぶキャストも青春映画らしい初々しさ。しかし、予告で見る限り、物語については謎を漂わせるテイストとなっています。
「階段島」という特異な舞台設定が果たして彼らの青春の1ページとどう交わり、結ぶのか。これについても期待して鑑賞しました。
以降、ネタバレを含んだ感想を述べていきます。未見の方はご注意ください。
68/100

目次
階段島とは何なのか
目を覚ますとそこは「階段島」。なぜ、どのようにしてここへやって来たのかもわからぬまま、他の2000人の島民たちと同様に諦観とも達観ともつかぬ形で状況を受け入れる七草(横浜流星)。ある日彼の目の前に、かつて別れた幼馴染・真辺由宇(飯豊まりえ)が現れる。彼女は島の秘密を解き明かそうと言い出すが…。
物語は大きな謎と共に幕を開ける。物語を追うにあたって当然の関心ごととなる登場人物の人物像よりも先に、彼らが階段島に連れてこられた経緯と理由が気にかかって仕方がない。階段島に住む人たちは一様に大切なものを失ったらしいが、それはどんなものなのか。この島を管理しているという魔女とは一体何者か。階段島とは何なのか。あまりに謎に満ちている。
真辺由宇と共にそれらの謎の解明に当たるミステリー要素がありつつも、基本的にはそんな彼女に引っ張られる七草やクラスメイトの面々が織りなす人間模様はいかにも青春映画らしい。
身に覚えのある階段島の住人たち
みんながおとなしく島のルールに従う中で、真辺由宇だけはそれに反発し、謎を解明しようとする。七草曰く理想主義者である彼女にとって、一方的にルールを押し付けられる理不尽には耐えられないし、自分たちが立たされている状況を知る権利もあるのだ。だから、あらゆる手を尽くして島の秘密に迫ろうとする。時には船で島外に出ようとするぐらいバイタリティーに溢れていて、他人に自分の考えを言う際にだって容赦はない。飯豊まりえは今作において口調は文語的ではきはきとしていて、表情も大きくは動かさない。真辺由宇の真四角な思考と、それを周囲と比較して顧みない大胆さが伝わってくる。
そんな彼女を一歩引いて見る七草は、島の秘密を解明することに対しては真辺由宇ほど積極的ではない。幼馴染だったという彼女と再会しても喜びを素直に表現することもしない。それどころか、かつて彼女と離れ離れになる際には笑みを浮かべる。七草が真辺に対して向ける感情の正体は何なのだろうか。そう思いながら映画を追っていくことになるわけだが、横浜流星の佇まいがそれとなく真辺に抱える感情を伝えてくれる。側にいたいと願う普遍的な愛情とは異なった、アンビバレンツな思慕が彼の切なげな顔つきによって訴えかけられる。
松岡広大演じる佐々岡は、新作ゲームを早く遊びたいという言動からも分かる通り、はやる気持ちを抑えきれずに突っ走る。今作では弦が切れてしまい、発表会で演奏できなくなってしまった豊川にとってのヒーローとなるため、魔女探しに乗り出す。大人になってしまうとなかなか出会えない、無邪気で活発な学生だ。
水谷は、丁寧な言葉遣いと応対で常に周囲を気遣う。それが保身的な思考であることを自覚の上で苦悩を抱えもいる、これまた思春期に陥りがちな複雑な心理状態である。自己主張も容赦なしの真辺とは真逆に、周囲との協調を図るばかりに自分を外に出せない彼女は、誰もが見覚えのある自分のかつての(あるいは今の)姿ではないだろうか。
そして、バイオリン奏者の豊川は、演奏がしたいという気持ちと失敗への恐怖を抱えている。かつて味わった挫折感をもう二度と味わうまいと、逃避にはしる彼女の姿もまた他人事とは思えない。
そう、この階段島に住む人たちはみんな我々とどこかが通っている。彼らが見せる言葉や行いといったものは、とてつもなく青く、気恥ずかしさすら覚える。時間が経てば、それは懐かしむべき対象になるぐらいに未熟なのだ。けれども、ふしぎと嫌悪感は湧いてこない。通り過ぎたら二度とは戻ってこないであろうその青さこそ、大人になってしまった自分たちが持ちえないものなのだから。

(C)河野裕/新潮社 (C)2019 映画「いなくなれ、群青」製作委員会
いつかは捨てなくてはならないもの
そんな在りし日の自分たちがいるような群像劇の果てに、階段島は大人になる段階で自分たちに脱ぎ捨てられた人格の集積場だと明かされる。これに驚くと同時に、何も意外なことではないとも気づく。
水谷のように自己を閉じ込め周囲を宥めるようにして良い人でありたいと思ったり、佐々岡のように誰かにとってのヒーローにないたいと願って突っ走ることは、誰だって経験があるだろう。失敗に怯えて弦を自ら切ってしまった豊川の心の揺れ動きも、日々の中ですり減らし、いつかは均されていく。人はそれを成長と呼ぶが、諦めとも言い表せる。
人口が2000人程度だという階段島の景色には子どもの姿が多い。これも考えてみると、上記のような人格を脱ぎ捨てるタイミングがちょうどそうしたタイミングになりやすいということを示しているのかもしれない。もちろん、成人してから不要な人格を捨てる人もいるが、作中では年配の人の姿は(記憶している限りで、だが)見当たらないので、やはり人生の若い段階で人格は形成されるとでも言いたいのかもしれない。
失くしたものを見つけることで元の場所に戻れるという作中のルールも、この未熟とみなされた人格に由来するのだろう。未熟とみなされて捨てられてしまった階段島の住人たちは、ある目的を持っていて、具体的なケースとして豊川が描かれている。彼女は晴れ舞台での失敗に対しての恐怖を抱えた人格だ。それを克服する過程が作中の捜査劇と並行して描かれており、結果として真辺らに後押しされた彼女は見事に演奏を最後までやり切るのだった。恐怖に打ち勝った彼女は、捨てられた存在という枠を超えたことになる。だから、捨てられた者たちの集積場である階段島から脱することになる。
今作では七草と真辺の回想を除いて階段島の外側は一切映らないため、自分で想像するしかないが、階段島の豊川は現実の豊川の中に還元され、そして消化されていったのではないかと思う。
捨てられたけど、ありえたかもしれない、もうひとつの未来
幸か不幸か、真辺由宇はその理想主義の人格をあるタイミングで放棄する。そして作中冒頭の七草との再会に繋がるわけであるが、それは即ち七草の持つ「ピストルスターのようにどこかで輝き続けて欲しい」という願いが潰えたことを意味する。
階段島ではない、現実にいる真辺由宇はきっと理想主義を貫くことに限界を感じ、諦めることによって、現実との折り合いをつけることになったのだろう。そして、作中では七草がこの島にやってきたすぐ後に同じ高校の制服を着た彼女と出会ったことから、七草は自分たちが再会し、そのままではいられなかったことを推測する。七草たちは変わり、かつての関係ではいられなくなってしまったのだ。
この映画が面白いのは、人の成長を必ずしもプラスとも捉えていないところだ。一般には、不要と判断した幼さを自分から引き剥がす行為を、人はみな成長と形容する。けれども、人の性質とは広く見れば上下のパラメータで測れるものではない。何を良しとし、何を悪しとするのかは、結局のところ自分たちの好悪によるものである。現に人の道を外れた行いが戦時には賞賛されたり、合理的であるはずの行動選択が社会的な圧力によって挫かれてしまう光景はいくらでもある。
つまり、人格を捨てて変化することは、ひとつの可能性を放棄することと表裏一体なのだ。捨てた側はそれを以って、ステップアップを図るのかもしれない。しかし、捨てられた人格にとっては否定され、見放されたも同然である。七草が悲観主義で、真辺が理想主義である限り、彼らの関係はうまくいかないという判断を、当人たちは異なるタイミングで下す。そうすることで現実の彼らはうまくいったのかもしれないが、もはやかつての彼らの関係たりえない。
しかし、最後の最後にこの作品はもうひとつの可能性をすくい上げる。真辺は階段島に戻ってきてしまう。もしかすると、現実で彼女の理想主義が再発したものの、またも捨てられたということなのかもしれない。ただ、そうした過程はどうであれ、放棄された人格はここで共生することを決意する。お互いの手を握る七草たちを見ていると、諦めてしまった物事には漫然として可能性が残されていたのではないかと思えてくる。捨てざるをえなかったあの考えや感情は間違いなんかじゃなく、きっとそれはそれでもうひとつの可能性だったのかもしれない、と。
一度は「いなくなれ、群青」という言葉を告げて、群青色の空に浮かぶ星に擬えて真辺を送り出そうとした七草の胸には、単なる恋慕とは異なったいじらしい尊敬の念と後ろめたさに満ちていて、奇妙な共感を覚える。そんな後ろめたさを突っ切って舞い戻ってくる真辺も一筋縄ではいかない。彼らの今後を考えると大変そうだが、それもまた楽しそうだ。

(C)河野裕/新潮社 (C)2019 映画「いなくなれ、群青」製作委員会
小説の世界に忠実すぎる側面
今作の登場人物、特に主人公の七草と真辺に関しては、文章に書かれた固い口調でものを語る。「アンケートで好きな星を聞かれたら、僕はピストルスターと答える」という言い回しひとつとっても、なかなか生身の人間が発しそうにない。原作を読んでいない自分から見ても、とてつもなく原作に対する信頼と拘りを感じさせる脚本である。
また、カメラや舞台美術についても同様で、この階段島の生活環境に漂う匂いが細かな小道具や光の具合で表現されている。古めかしい日本家屋の中に飾られている金魚鉢や年代物に見える時計など、写り込むのは極小ながら、着実に現代社会とは切り離された時間の停滞している様を演出している。
ただ、これらの強い拘り故なのか、あらゆる現象を懇切丁寧に言語化、ないし可視化して説明しているきらいも見られる。
例えば、七草が語るピストルスターへの憧れ。それが最終的には真辺へ差し向けた感情と重なるものであると明かされるのだが、事細かに口で説いてしまうものだから、想像に委ねてくれる余地は思いの外少ない。横浜流星の物憂げな表情を見ていれば、映像で察して自分の頭の中で増幅させることだってできるのに、言語で制約されてしまうようで惜しい気分になる。このように、作品に漂う曖昧さを重んじるような空気とは相反して、言語で具体的に言ってしまう場面が多い。
情報量の多い小説を映像に持ち込む上で、何を語らず、何を語るかという取捨選択は非常に困難な作業になることは想像に難くない。とりわけ今作のように、ミステリーの体裁を持っている以上、情報を明かしていく過程は慎重にならねばならないだろう。ただ、終盤に登場人物の心情、及び階段島の謎の解明が偏っているので、結果的に中盤部分までの過程はそれらをはぐらかしているような印象さえ受けてしまう。これには、映像面での外連味を感じられる部分が、教室の黒板に書きなぐるシーンぐらいで、全体を通してかなり少ないというのも一因ではある。
詳らかに小説の世界を再現するというアプローチとしては真剣ながら、この手の忠実さは時に映像作品にとってはっきりとした一長一短を生むのかもしれないと思った。
まとめ: 反現実によるメッセージ、そして片山萌美
この作品に流れるのは、今夏公開された『天気の子』にも近い精神だと思う。現実では悲惨なことに見舞われている者たちの幸福を描こうとしている。『天気の子』では矢面に立たされ理不尽を一身に背負う存在が、その宿命から脱しようとする様子を描いていた。『いなくなれ、群青』は放棄され、否定されてしまった人格たちの営みを描き、最後には彼らの存在が間違いではなかったことを証明するという決断に至る。
脱却したかつての姿を振り返らせるなんて、こうしたフィクションでしかなし得ない所業である。現実に反抗する形で導き出されるメッセージも意外性がある。また、少しだけ過去に置いてきた物事にも別の選択があったかのような感覚を抱かせられた。単にありえない設定を置くのではなく、そこから見ている側に通底する何かを訴えるというのは、やっぱりフィクションの醍醐味のひとつだ。
今作は、『L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。』『チア男子!!』で目を付けた横浜流星に惹かれて観に行ったのだが、意外にもサポーティングロールで登場する片山萌美に目を奪われる時があった。学生の七草たちを目上の立場で見守る姿がとてつもなく板についているし、余裕があって奥底に何かを秘めた雰囲気が頭に残る。最近の映画では『万引き家族』等、登場時間が少ない役柄が多いが、もっと堂々と活躍してくれるのを密かに期待しておく。
関連記事: 日本映画の注目株・横浜流星
▼赤く染めた髪の毛でわんわん吠える犬みたいなキャラクターを演じた『L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。』
▼男子チアの道に足を踏み入れ、仲間たちと練習に励む等身大の大学生を好演『チア男子!!』