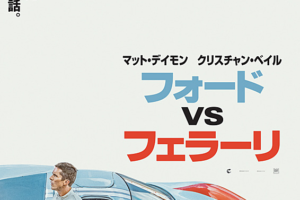アイキャッチ画像: (C)2019 VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED, WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC
こんにちは、裁判傍聴を趣味にしてみたいワタリ(@wataridley)です。
今回はクリント・イーストウッド監督作『リチャード・ジュエル(原題: Richard Jewell)』の感想を書いていきます。
リチャード・ジュエルは、1996年のアメリカ、アトランタオリンピックに際して行われた屋外コンサートの会場に設置されていた爆弾を発見し、その被害を抑えたことで知られる実在の人物です。その功績が讃えられる一方で、第一発見者であることからマスメディア及びFBIから真犯人であるとの嫌疑をかけられ、苛烈なバッシングを浴びせられました。
そんな苦境に立たされた人物を扱う今作は、凶悪事件に立ち向かった英雄譚という趣きは控えめで、寧ろ正しいことをしたにもかかわらず、謂れのない疑いをかけられてしまう理不尽な状況に対し、静かな怒りをぶつけた作品のようでした。
端的に言ってしまえば、冤罪事件をテーマにした作品ですが、今作はイーストウッドの優れた演出力、情報の見せ方、そして俳優のリアリスティックな演技によって、過去に起きた過ちというよりも、この世界に今も起こっている景色のように実感させてくれます。特に、誰もが情報を発信でき、根も葉もない噂や誹謗中傷が蔓延する現代において、今作で描かれる出来事は、鋭い指摘を現代に投げかけているように感じられました。
以降、ネタバレを含めた感想を書いていきます。未見の方はご注意ください。
70/100

目次
爆弾テロの犯人像に引き寄せられた人生を取り戻すドラマ
爆弾を防ぐ要因としてのリチャードの真面目さ
物語は、リチャード・ジュエルが法律事務所の備品係として働いていた時から幕を開ける。そこでは後に彼の弁護士になるワトソン・ブライアントが所属しており、2人はひょんなことから親睦を深めることになる。
この冒頭のシーンはなんてことのない人間関係の始まりのように映る。しかし、後にリチャードが見舞われる悲劇と照らし合わせることで、実にピュアで温かい交流に様変わりして感じられるからふしぎなことである。大の大人が2人並んで射撃ゲームに興じる画は、それだけで和やかだが、ここで銃の腕と絡めて、リチャードの法執行官への憧れを口にさせる。映像によって彼らの交流と将来を見据えさせる地味ながら優れたやり口で、冒頭から引き込んでくる。
そして法執行官を志すリチャードは備品係の職を辞めた後は、一度副保安官として働くもののクビになり、大学やイベントの警備員を務めるなどして職を転々とする。その過程においても、彼はスニッカーズにも通ずる仕事熱心ぶりを披露する。大学では学生寮の寮生に飲酒を問い詰め、果ては校外で車のスピードまでも取り締まるほどだ。学長の過去の発言も事細かにメモを取り、呆れられる一幕もあったが、あくまで仕事に入れ込んでいるがためのものである。しかし、その行為を行き過ぎだと指摘され、仕事を辞するよう言われたように、なかなかに彼の仕事が社会的に評価されることはない。
しかし、愚直とも揶揄できてしまうくらい実直な勤務態度が、野外コンサートの会場でいち早く爆弾を発見し、被害を最小限に抑える要因となるわけだ。何もそこまですることはないだろうと乗り気でない警備員や警察の姿も途中に映るが、もしその場にリチャードがいなかったらと思うとゾッとする話である。結果として、爆弾の炸裂により放出された無数の釘による111人の負傷者と、2人の死者(うち1人は爆発後の心臓発作による)が出てしまったものの、観客があのまま舞台上に夢中でいたら、死者はより拡大していたであろうことは想像に難くない。
大多数の分子の流れに逆らうようにして行動をとったリチャードという異分子のおかげで、より悪しき事態は免れたわけで、これは歴史上において英雄と呼ばれた人々の姿とも重なる。偉業を成し遂げる人は、定説を覆すべく異説を唱え、それによって白い目で見られたり、疎まれたりするものだ。自分たちのいる場所がテロの標的になっているなんて夢にも思わない緩い空気の中、危機を察知し、いち早く動いたリチャードは、天動説に対して地動説を唱えたコペルニクスに喩えることもできる。
爆弾発見の原因が犯行に結び付けられてしまう理不尽
だが、リチャードのもつ人並外れた部分は、不幸にも、事件の引き金ではないかという嫌疑の的となってしまう。国際的なイベントにおいて発生したテロ事件にも関わらず成果を挙げられない状況に苛立ったFBIの捜査官達は、「英雄を装う第一発見者」という像をリチャードに当てはめ、目をつける。
捜査の手はリチャードのプレイベートにそれとは気づかれない形で及んでいく。ある時は盗聴器をつけて自宅に入り、またある時は捜査協力の名目で密室で自白を取ろうとする。相手は犯罪や法律に関して熟知している捜査官で、自分はただ1人という状況は圧倒的に不利だ。容疑者と疑いわれ、つけ狙われてしまえば、不利な情報を引き出され、まんまと陥れられてしまうほどに市民とはか弱い存在なのだ。
幸運にも弁護士ワトソンと通じていたリチャードは防犯ビデオの撮影に疑いを持ち、彼に連絡を取ることができたが、ちょっとでも再会の連絡が遅れていたらどうなっていたことか。また、連絡を受けたワトソンも一度はリチャードは不在だと突き返されている。司法機関に告発するぞと啖呵を切ってようやく取り合ってもらえたが、秩序を守るはずの捜査機関も容疑者を捕らえるためなら手段を選ばないということが窺えて、なかなかに恐ろしい描写だと思う。
また、こうした捜査の動きと並行して、マスメディアはリチャードのプライベートを暴き、犯人像に似せて彼を報じるようになる。映画においては、オリヴィア・ワイルド演じるアトランタ・ジャーナル・コンスティテューションの記者キャシー・スクラッグスが、ジョン・ハム演じるFBI捜査官のトム・ショウと癒着し、スクープのネタを手に入れたとされている。公権力を監視し、社会的に果たす役割も大きいことから、「第四の権力」とも呼ばれるマスメディアまでもが敵に回れば、本当に個人には抗いようのない危険に晒されることになる。マスメディアが大衆受けを狙って個人のプライバシーを蹂躙してしまう様子も、これまた飽きるほど見ている。
慎しく母と2人で暮らし、職務を全うしただけの彼に、メディアリンチと捜査機関が襲い掛かる様子は、前半ではじわりじわりと描写されていき、防犯用のビデオ撮影の件以降、いよいよ過激になっていく。
何気なく彼の人生を構成していた法執行官への憧れ、決して裕福とは呼べない母親との2人暮らし、趣味の射撃といった諸々の要素が、事件の犯人と疑われた途端、あたかも悪しき事のように取り沙汰されていく様は、理不尽極まりない。捜査の手は過去の出来事にも容赦なく及んでいき、大学の警備員としての勤務態度や、子供時代に爆弾を作ったという友人の証言も、不利な情報として扱われてしまう。
残念なことに、これはフィクションでも、この事件に限った話ではない。また、その状況を生む主体はマスコミや警察に限られているわけでもない。むしろネットとSNSを使い発信者となった我々は、日々誰かの言動の揚げ足を取り、過去の発言からその人の人格についての偏見を浴びせる。ひどい場合には根も葉もないデマがあたかも真相かのように語られていき、しかしそれがやはりデマだと判明したところで、誰も責任を取ることはない。
ここ数年、「フェイクニュース」という言葉が登場し、意識されるようにはなってきた。これは、四方八方から雪崩れ込んでくる情報を逐一精査する機関はなく、各々がメディアリテラシーを以て対処していかなくてはならない時代性が生んだ言葉だと個人的に解釈している。国家が情報を操作することで国民を扇動するといった事態は戦中にも見られてきたし、マスメディアによる誤報や利害に絡んだ偏向報道とされる事例は挙げればキリがないが、近年のネットワークの発展によって、以前よりも増して「リチャード・ジュエル」を生むリスクが高まっていると言える。
リチャードの直面した事態は、裏返せば日々我々が大なり小なり与していることに過ぎない。しかし、ターゲットとなっている当人からすれば、尊厳に関わるほど深刻な事態なのである。
権力の欲にのまれた側とリチャードの対比
そんな窮地に立たされたリチャードを旧知の関係にあったワトソンが助けるというのは、彼に疑いをかける者達とは、くっきりとしたコントラストを放つ。彼は元よりリチャードの熱心な仕事の姿勢を知っているし、法執行官への憧れを耳にしている。何のフィルターも介さず、その人柄を知っている彼がリチャードを弁護するということは、直接的にリチャードを知らずに外面的な経歴や人伝の言動でしから知らずに疑いをかけている捜査官やマスメディアと正反対だ。
思えば、2人が距離を縮めるきっかけになったのは、ワトソンが机に補充していた業務用の備品のみならず、彼が愛好しているスニッカーズまで気を使って補充するほどのリチャードの過ぎるくらいに真面目な勤務態度だった。それが爆弾の被害を抑えたとも言えるし、窮地に陥っても尚社会正義を尊重するリチャードの姿を間近で見たワトソンにとって、彼の弁護は単なる依頼ではなく、友人の尊厳をかけた戦いという意味合いも帯びていたはずだ。
そのワトソンが作中でリチャードにかけた言葉のうち、100ドル札を引用して語った台詞がリチャードと彼に疑いをかける者達との間の隔たりを如実に示していた。100ドル札に書かれた「quid pro quo(交換条件)」というフレーズに重ねて、法執行官になる彼に、権力を振りかざすようなクズになるんじゃないぞという忠告を送る。
この言葉を反芻すると、自身のもつ権力故に傲慢に偏ってしまった者が、あの記者とFBI捜査官だったのではないかと思えてくる。FBI捜査官はリチャードを狡猾に陥れようとする過程で、「同じ法執行官だから」と捜査協力を頼む体裁で彼から不利な情報を引き出そうとするやり取りが見られるが、一方であきらかに見下していると思しき態度をちらつかせる。単なる警備員であり、疑わしい者であるリチャードに、どんな手段を使ってでも陥れようとする傲慢さも、法の執行者として権力を持ってしまっていることからくるのかもしれない。マスメディアに関しても、リチャードを典型的なホワイトトラッシュに当てはめて報じたように、一市民の人権をも軽んじてしまう危険性を常に孕んでいる。
我々を苛立たせるものこそが彼の強さ
一方で、今作を観ていると、少し苛立ちを覚える描写も散見される。それは主にリチャードの振る舞いについてのものだ。というにも、この映画は必ずしもリチャードを英雄的に描こうとはしていないことから、こうした感想に至る。
例えば、リチャードがコンサート会場で警備の仕事をしている時、ミリタリーバッグを抱えた怪しげな男の後を追い、それがただの杞憂だったとわかる描写。爆発事件が起こる前日ではあるため、この疑いようは当然と言えば当然であるが、一方で彼の勤務態度が行き過ぎていると感じさせる描写になっている。リチャードの評判として作中で言われるちょっとやりすぎではないかという印象は理解でき、故にマスメディアによる報道に、憤りを感じるのと同時に納得できてしまう感覚もある。
また、爆発事件の翌日に木片を拾っていたり、「ゾンビでいろ」と言われたにも関わらず捜査協力を申し出たり、まんまと誘いに乗って犯人の台詞を録音させてしまうなど、色々な隙を見せてくる。
しかし、自分が感じていた苛立ちにも今作は回答を用意している。一見軽率に見えるリチャードの行動はいずれも、法執行官としての正義感のためであり、本当はFBI捜査官から見下されているのだと知っても尚、へそを曲げずに踏ん張っていると知ると、彼の強さを思い知らされることになるのだ。
主演のポール・ウォルター・ハウザーの、真面目すぎるが故の融通の効かなさを体現した、ちょっとウザいとも言える振る舞いは、彼を美化しすぎず、こちらの心配を誘う点において非常に巧妙だった。こちらの思うように言葉を語らず、じわりと追い詰められ続ける彼が、終盤に自らの言葉で語り出す場面は、生優しく事態に流されているように見えたそれまでとは対照的に、胸がスッとするような力強さを感じた。
あくまで個人の勝利として
リチャードへの疑いは結局事件から約3ヶ月後に取り下げられることになるわけだが、今作の勝利の描き方には、個人への尊重が根差しているように見受けられる。というのも、あれだけ騒ぎ立てていたマスメディアや、それを見ている大衆の描写は抑制されているからだ。画面に映るのは、レストランで座っているリチャードとワトソンの2人が抱擁を交わす姿であり、勝利の瞬間がリチャード個人を直接知る者達によって決定づけられている。また、今作のラストシーンもワトソンが真犯人が捕まったことをリチャードに告げにきた場面となっている。
もし、本人を直接知らない外野がリチャードを無罪だと認める描写があろうものなら、それはリチャード個人を軽んじた結果と映りかねない。一方で、今作のリチャードとワトソンの2人に着地を委ねたことで、彼の生真面目な性格や仕事の姿勢を自分達で証明したというニュアンスを持ち得るのだ。リチャードの軌跡は、爆弾テロの原因ではなく、たしかに多くの人の命を救う原因だったのだと自分達で認められることを重視して、この結末にしたのだろうと思う。
シンプルな人間の勝利を描いたラストは、単なる爽快さを狙ったものでもなく、国家や大衆といった大きな単位よりも個人を尊重してきたイーストウッドの狙いにも見える。他方、家宅捜索により持ち去られたタッパーに書かれた整理番号を見つめる母バーバラの目は安堵と疲労を感じさせるが、一度は国家権力によって市民の生活が歪められてしまったことへの静かな怒りを見せつけてくるようであり、喜びばかりというわけでもない。
今作は、こうしたメディアリンチへの警鐘、国家権力への批判的な視線、そして大勢から逸れてでも命を救う行動に出た個人の尊重を描き、1996年の話でありながら、現代にも通ずる痛切なメッセージを届けている。
マスメディア絡みの描写に見える単純さ
そうした評価したいと思える部分が大半を占めているとはいえ、今作には首を傾げたくなるような描写もある。
まず、アトランタ・ジャーナル・コンスティテューションの女性記者が、FBI捜査官からセックスと引き換えに捜査情報を得ているかのような描写は、眉を潜めざるを得ないところである。その描写自体が「性を売りにする女性」というステレオタイプを特段の工夫もなくやってしまっているという点で安易さを感じる。
何より、この一連の描写は真偽が不明であり、製作側の推測を交えているという点に注意が必要だ。この件については、アトランタ・ジャーナル側からも抗議の声が上がっており、更にイーストウッド側が反論するという事態になっている。渦中のキャシー・スクラッグスはすでに故人であり、正確な真偽確認はできない。そんな中で今作がこのような描写をしてしまっては、残念ながら、人にレッテルを貼る行為にほかならない。そしてそれは作中で悪しきこととして描かれており、明らかな自己矛盾である。
特に今作の登場人物の中でも、キャシーはスクープ目当てにリチャードを貶めた発端として描かれており、のっけから自身の容姿をも仕事の売りにするかのような発言や、リチャードの外見を犯人像に結びつける著しいルッキズム等、醜悪さを印象付ける描写も多い。このあたりは、「死人に口無し」をいいことに、自分達のいいように人物を曲げて描いているという批判が出てきても仕方ないだろう。
また、そうしたキャシーのキャラクターにマスメディアの過ちをすべて集約させてしまっていることにより、メディアリンチに関する描写は今作でも思いの外深みが感じられない。基本的に、今作でリチャードにあらぬ罪を着せるマスメディアの筆頭はキャシーであり、他の会社に関しては一緒くたに背景としてしか描かれていない。彼女だけは、他社を出し抜いてリチャードの容疑に関する記事を出す、勝手に車に乗り込んで取材を試みるといった具体的な行動が描かれるが、どれも思慮浅はかでデリカシーもないだけであるため、その人物に立体性を見出すことが困難である。
それでいて、バーバラの会見を以ってメディアリンチが終息の兆しを見せることの描写も、彼女に一任されてしまっており、メディア周りは軒並み単純化された印象を受ける。今作には他のマスメディアの影が薄く、またメディアの受け手が事件をどのように見ていたかについても省略されているが、それらの役割を極端なキャラクター付けのなされた彼女1人に委ねるのは、無理があったような気がする。
まとめ:過去から学び今に活かせるか
『リチャード・ジュエル』は、「疑われた英雄」という題材が共通する近作『ハドソン川の奇跡』を彷彿とさせる作品であるが、より踏み込んで疑惑が英雄を蝕む描写に注力することで、社会が英雄をどう扱うのか?という問題提起を強めた作風になってるように感じられた。特に、現代では我々がこうした偏見を生みかねない主体者になっているため、他所の国で起きた出来事として済ませられない身近な恐怖感を覚えた。
冤罪事件という点においても、むしろ日本の方が起きてしまった場合には取り返しがつかない環境にある。リチャードは身柄を拘束されることはなかったが、代用刑事施設制度のある日本で拘束されれば最大23日間も留置場も留置されることになる。取調べに弁護人が立ち会えるアメリカとも異なり、弁護人もいない中で外部から不可視の密室で取り調べを受けることにとなれば、自白を強要されかねない。故に、冤罪の温床だという国際的な批判もなされてきた。
最近では、別件逮捕により勾留期間を伸ばされ、長期に渡って拘束されたカルロス・ゴーンが仮釈放期間中にレバノンに国外逃亡したニュースがインパクトを残したが、ある意味でこうした日本の司法制度の問題点を再認識させるきっかけになっていた。この件に関して、法相が「無罪を証明すべき」と推定無罪の原則を無視した発言をし、未熟さを露呈してしまっていたが、今作の劇中においてワトソンの事務所の秘書であるナディア(おそらくロシア出身)の「自分の国では国家が有罪だと決めたらみんな無罪だと思っていた」という台詞がまさに皮肉のように頭に響いてくる。
冤罪事件とは人為的なミスにより起こってしまうものとはいえ、起こさないよう努めるのがあるべき社会の姿勢である。英雄が犯人と間違われてしまうこの不条理なシーンを振り返らせることで、安易に人を見た目で決めつけるような日常の行いに至るまでを省みさせようという意思が込められた映画に映った。
関連記事: 歴史を振り返る米映画
▼アメリカのすべてをこの副大統領に委ねて何が起こったか『バイス』
▼月へ行くという国家の一大プロジェクトの中にある個人の内側『ファースト・マン』