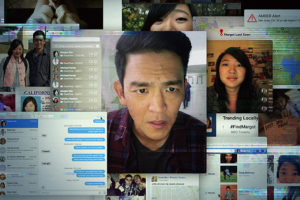こんにちは、最近お肌がカサついてきたワタリ(@wataridley)です。
今回はレバノン・フランス合作映画『判決、ふたつの希望(原題: L’insulte)』を観た感想を述べていきます。
レバノンという国は日本から遥か遠くにあるばかりでなく、それほど深い関係があるというわけでもないようです。そんな国で製作された映画が日本で上映され、観た人からの高い評判も漏れ聞こえてきたため、劇場へ足を運びました。
この映画は、そうした文化圏の違い・地理的距離をまるで意識させない普遍的なドラマを孕んでいました。謝罪という行為ひとつを通じて人が抱える偏見と敵意を明らかにし、どのようにしたらそれが解きほぐされるのかに対して堅実な回答を出しています。誰もが経験する原始的なディスコミュニケーションとコミュニケーションの両方がここにあるのです。
法廷劇の一面を持っているため、激しい論争が巻き起こる場面もあり、緊張感を煽られるサスペンスものとしても一級品でした。
ネタバレを交えて展開に対する私感を以降記しています。
77/100

はじまりはささいなこと
物語の発端は実にちいさなこと。違法建築の修理工事の最中、取り付けた配水管を住人が壊してしまい、それに立腹した現場監督が彼を罵ったというもの。
この時点では、よくある工事トラブルのよう思える。監督の上長は穏便に済ませようと謝罪の意を住人のトニーに示しているし、監督のヤーセルも上長に説得されて渋々トニーのもとを訪ねている。
だが、レバノン人とパレスチナ難民というエスニシティの壁が、コトを複雑にしてしまう。ヤーセルはトニーの職場に流れていた反パレスチナ難民の政党演説に気分を害し、形ばかりの謝罪さえできなかった。それどころか罵られた際の激情を行動に変えてしまい、トニーに怪我を負わせてしまう。
ヤーセルばかりが一方的に悪というわけではなく、彼の境遇や生い立ちを侮辱したトニーも糸を絡ませた張本人である。そもそも、ヤーセルの訛りを耳にしたトニーが彼を部屋に入れなかった行為も発端のひとつだ。
トニー・ハンナを演じたアデル・カラムのドスの効いた声は、見る側にヤーセルが受けたのと同じような嫌悪感を与える。皺の寄った眉間が似合う顔つきが、パレスチナ難民に対する疑心を表していた。ヤーセル役のカメル・エル・バシャはどこか枯れていて、穏やかそうな人柄に映る。それだけに、トニーに罵られた際の苛立ちや解雇通知への狼狽にこちらの胸も苦しくなる。当初はギラついているが徐々に内面が見えてくるトニーと、落ち着きを徹しきれず感情敵になってしまうヤーセル2人の人間臭いキャラクターが、この映画をノンフィクショナルな雰囲気に染め上げていたのは言うまでもない。
彼ら2人の差別や対立を煽る事情が裁判によって白日の下にさらされ、世論は熱を帯び、火車のように収まらなくなってゆく。些細な出来事に端を発し、国内を揺るがしていくという過程が実に自然な流れで描かれていくのが恐ろしい。冷静に考えれば個人と個人の喧嘩でしかないことを、世間は民族性の対立として祭り上げ、一触即発の状態に陥ってしまう。人間はこうも簡単に争いの火種を広げてしまえるのだと思い知らされる。

(C)2017 TESSALIT PRODUCTIONS – ROUGE INTERNATIONAL – EZEKIEL FILMS – SCOPE PICTURES – DOURI FILMS
PHOTO (C) TESSALIT PRODUCTIONS – ROUGE INTERNATIONAL
やがて国家を揺るがす対立へ
2人の問題は簡単に解決できたはずだ。片方が謝り、あるいはもう一方が許容すれば済んだことだろう。
もつれ込んで裁判沙汰にまで発展したものの、結局ヤーセルは殴ったことの非は認めているし、トニーは謝罪さえ貰えればそれでいいという立場で、最初の公判で形ばかりの白黒はつくはずだった。
ここで決定的に問題をややこしくしたのがトニーがヤーセルにかけた「シャロンに抹殺されていればな」というひどく攻撃的な言葉である。トニーはこの言葉を自ら口にすることを躊躇うほどにその意味を理解していた。そして、ヤーセルも口をつぐんだ。公の場で言うには相応しくないという共通認識が見て取れるし、ここに限れば対立は無い。
だが、裁判官の一存によりトニーは不服な処遇を受け、ヤーセルも謝罪の機会を逃してしまうことになる。
更に、控訴審にて付いた弁護人が、彼らの個人的な内情を軽んじ、主体的に物語を引っ張っていく。ここを境にトニーとヤーセルがみるからに物語からも軽んじられていくのだ。
控訴審で繰り広げられるのはトニーとヤーセルの会話などからかけ離れた、両弁護人による激しい論争だ。原告、被告の関係者を法廷に招き、利益的な情報を引き出そうとする駆け引きが論理的な台詞回し、時に煽り立てるような物言いで語られる。小柄な身体から漂ってくる知的な老獪さと感情を交えた弁で攻勢に回るワジュディーと、彼と対照的に冷静さを保ちながら論理的な話術で守りに徹するナディーンの舌戦はたいへん見応えがある。この裁判シーンの臨場感だけても劇場で価値がある。論争に見慣れた頃合いに、彼らが実は親子だったという事実を明かす仕掛けもあり、飽くことなく興味は引かれ続ける。
裁判の合間に世論が過熱していく様がドキュメンタリータッチなデモや衝突、報道風景で軽やかに語られる一方、ヤーセルは職を失い、トニーも脅迫紛いの嫌がらせを受けるといった緊迫した事態が挿し込まれている。もはや事態は彼らが制御できる域を超えてしまったのだ。
実際この中盤の法廷シーンでは、トニーとヤーセルがカメラに映り込む時間が劇的に減っていたように思う。お互いこんなことは望んでいなかったのに、という彼らの胸の内は過熱した状況を見れば一目瞭然である。
トニーとヤーセルの個人的な対立を他者が社会的問題と拡大解釈し、事態が激化していく様は、スリリングであると同時に、とても居心地の悪いものであった。

(C)2017 TESSALIT PRODUCTIONS – ROUGE INTERNATIONAL – EZEKIEL FILMS – SCOPE PICTURES – DOURI FILMS
PHOTO (C) TESSALIT PRODUCTIONS – ROUGE INTERNATIONAL
共感が謝意を呼ぶ
人身事故や裁判所内での激しい口論など、過度に強まった熱は収まるところを知らない。2人のこじんまりとした発端などもはやとうの昔のように思える折に、彼らは原点に立ち返る機会を得る。
レバノンの大統領に召集され、混乱を収めるために折れるよう要求された帰り道にトニーは、車が動かず困っていたヤーセルを車修理工の知識を駆使して手助けする。官邸や裁判所といった公の場所では対立していた2人が、ネクタイをゆるめるような非公式の場では1人の人間として相対したのだ。レバノン人とパレスチナ難民という飾りつけはここでは外れ、相手が困っているのを見過ごせずに助ける人間味にほっと一息つけるシーンである。
トニーはたしかに意地悪に謝罪を要求してしまうし、妻に対しても横暴な態度を取ってしまうこともある。しかし、根っから本人が悪いことをしたいと思っているはずがない。人が困っている時にふと親切心が芽生えてしまうというのは誰にだって覚えがあるだろう。
裁判所でヤーセルの仕事関係者が「彼は中国製の重機を使いたがらない」と証言した時、トニーがおもむろに反応を示すシーンも印象的だ。これ自体は、本筋から外れた取るに足らない情報である。しかし、トニー自身も車に中国製のパーツを使わないよう指示していた経験から、彼が決して自分とわかりあえない異物でないことに薄々気が付き、あの反応に至ったのだろう。
この映画における裁判というのは、実のところカムフラージュに過ぎない。あれだけ白熱した弁護人どうしの駆け引きも、世論の動乱も、彼らの本意と離れたところで展開していからだ。
彼らは裁判とは無関係のところでトラブルを起こし、裁判とは無関係のところで和解した。その原因となったのは、「中国製」だとか「困っている姿」といった実にちいさなことである。40年前の村の占領事件とトニーとが結びついた時、ヤーセルの中でも意識に変革が起こった。トニーは自分と同じ故郷を追われた者だったと気づき、素直に謝罪に出向く。わざと挑発することで、殴られた側の痛みを自分も受ける。互いを国籍違いの異物ではなく、同じ痛みを感じる同類にしたのである。
最後にくだされた判決は周囲には安堵をもたらす一方で、彼ら2人の関係性において大きな意味を持たない。敗訴したトニーがヤーセルと視線を交わすその姿にこそ、この物語の真髄が詰まっている。
『判決、ふたつの希望』は異物化してしまえば簡単に対立できる人間の本能と、同一視してしまえば簡単に相手を受容できる人間の可能性を同時に描いた作品だ。

(C)2017 TESSALIT PRODUCTIONS – ROUGE INTERNATIONAL – EZEKIEL FILMS – SCOPE PICTURES – DOURI FILMS
PHOTO (C) TESSALIT PRODUCTIONS – ROUGE INTERNATIONAL
まとめ: 衝突の重要性
他方でこの映画は、謝罪することを何事においてもの善行として描いていない。あの時、すんなりと謝罪できていたら、表面上彼らは和解していただろう。チョコレートを素直に受け取っていたら穏便に済んでいただろう。難なく工事は進み、配水管はすぐさま取り付けられたことだろう。
しかし、これでは両者の間にある蟠りは残ったままだ。トニーにとってのヤーセルは排斥すべきパレスチナ難民として記憶され、ヤーセルのとってのトニーは差別的言動を取る過激派として終わっただろう。論理的に正しいはずの謝意なき謝罪を行ったところで、納得のいかない妥協をしたところで、人が人らしくあるための感情に決着はつかない。
彼らが衝突することによって、その蟠りが最後には解きほぐされることとなる。衝突を通じて彼らは自分たちが「同じ」であることに気づき、「同じ」だからこそ謝罪の言葉を発せられた。
衝突は時に傷を生むが、衝突することで相手を知る機会もまたある。本心を隠したまま表面上の平穏を保ったところで、内側で積もり積もった不平不満がいつかは噴出し、より大きな悲劇を生みかねない。そうならないよう自己主張し、相手からの主張も受け止める。
裁判を行ったからこそ、ヤーセルはトニーの過去を知った。
はじまりこそ「あの時、謝っていれば」と思わずにはいられないものであったが、終わってみると「ぶつかってよかった」という面もあるのではないだろうか。