アイキャッチ画像: (C)2019 映画「二ノ国」製作委員会
こんにちは、体育帽のゴム紐を装着するのが嫌で一切使わなかったワタリ(@wataridley)です。
今回は同名の人気RPGをアニメーション映画化した『二ノ国』のレビューを書いていきます。
原作『二ノ国』を手がけているレベルファイブはこれまでにも『イナズマイレブン』や『妖怪ウォッチ』などの人気ゲームを数多く手がけてきたゲーム制作会社です。今作の脚本を務めている日野晃博は、同社のゲームのシナリオも手がけており、それらのメディアミックスに際しても制作に関与しているようです。
氏が脚本としてクレジットされているアニメ『機動戦士ガンダムAGE』では、その奇妙な台詞やストーリーへの物議が観ていない自分にも聞こえてくるほどで、正直なところ、これで脚本に期待するのは難しいという状態でした。さらに追い討ちをかけるようにして、公開当日に鑑賞した人たちの間では、概ね酷評。
そのため、前々から惹かれていた原作由来のジブリ的なルックスに興味を持ちつつも、シナリオ面には全く期待せず、観に行くことになりました。
以下、ネタバレを含めた感想を書いていきますので、未見の方はご注意ください。
22/100

目次
ファンタジーの法則をペラペラ説明する工夫のなさ
ある日、突然通り魔に刺された幼馴染のコトナ(声:永野芽郁)をめぐってユウ(声:山崎賢人)とハル(声:新田真剣佑)は喧嘩を繰り広げ、あわや車に轢かれそうになった次の瞬間、彼らの目の前に広がるのは、異世界「二ノ国」だった。そこでコトナにそっくりの姫君アーシャを見つけた彼らは、危篤状態の彼女を救おうとするが…。
今作の導入では、まず現実世界における問題を描いてから異世界へトリップする。この手のファンタジーとしては頻繁に見られる構図である。今年公開された同じくワーナー・ブラザース配給の『バースデー・ワンダーランド』も同様の手法を取っている。現実世界で起きた問題を異世界の旅を通じて成長した主人公が解決するというのが、物語のゴールというわけだ。
作品内の現実に起きた問題がそのまま我々観客の現実に起きうる問題と通じ合うからこそ、ふんだんに彩られた旅風景やファンタジー要素で楽しんだあとは、現実に持ち帰る教訓を得ることができる。だから異世界ファンタジーは現実と異世界の双方を立体的に描くことが求められる。2つの世界という概念は安易に興味を引くことができるが、その期待に応えるには相当の魅力が必要になってくる。
悲しいかな、今作にはそうした異国情緒あふれる魅力というのは皆無である。本編の大半を、キャラクターが異世界の文化やルールをペラペラと語るつまらない画が占めていた。
まず、今作最大の特徴である「命のルール」について。異世界「二ノ国」は「一ノ国」と決して交わることはないが、双方の世界に住む人々は命がリンクしており、どちらかが死ねばもう片方も死ぬという法則があるとされる。今作では、ヒロインのコトナが命の危機に瀕すれば、彼女と命を共有するアーシャ姫も重篤に陥る。今作の物語における際重要事項である。
このルールは後半に差し掛かる時、「実はどちらかの命を救えば、どちらかの命が脅かされる」という覆しがなされる。しかし、その根拠は全く映像で語られることはない。もっと言うと、一切の根拠もない。コトナの体に悪性腫瘍が出来たのは二ノ国とは関係ないという見方もできるし、そのルールを信じるとしてもコトナが刺された時にアーシャが呼応するようにして危篤状態になっていた事象に対して疑念が生じるはずである。
そうした論理性が乏しい中、全て口述で偽のルールが語られていくので、観客は置いてけぼりにならざるを得ない。そのくせハルは、まんまと口車に乗せられて、殺人を決意するという突飛な行動に走っていく。そのハルの心情も全てが台詞で語られるがために、全く感情移入する隙間を与えてくれない。そもそも、あまりに浅薄な思考能力しかない彼に肩入れすること自体もまるで困難である。オマケにどちらかが生き延びればどちらかが死ぬという命のバランスが嘘っぱちなので、彼らが繰り広げていた争いそのものが茶番だったというオチに終わるから虚しい。
また、今作では現実世界と呼応するサンプルとして、コトナの他にもサキ姉が登場するが、これについてもペラペラとユウがその安否を語ってしまう始末。「ヴェルサさんが無事ということならサキ姉も」とか、言わなくても分かる情報をいちいち口走る。それは限られた上映時間を無駄に引き延ばしているだけだろう。
今作は台詞で語るばかりで、映像面では全く楽しみがない。クライマックスでいきなり登場する「聖剣グラディオン」も、台詞で存在を語り、台詞でそのおどろおどろしさを訴えるだけなので、どれほど凄いのがか全く実感できない。これがゲームなら「パワーアップアイテムが出てきたぞ」と喜べたのかもしれない。また、基本的に王宮で立ち話するシーンばかりで、世界の住人の暮らしぶりやファンタジーらしい旅風景がないために、妙に世界がのっぺりとして映る。一体何のために映像メディアでこれを語っているのか甚だ疑問だ。原作がRPGだというのに、王宮周りでの会話だらけという画の構成に疑問を持たなかったのだろうか。なんであの医師団の踊りに時間を割いたのだろうか。
中盤には飛行船に乗って遠出するシーンがあるものの、そこでも立ち話が中心で、RPG原作らしい冒険は繰り広げられない。「一ノ国」と「二ノ国」の関係性をアーシャの口から語らせるためのシーンでしかなく、ユウがアーシャと親しくなるにしても「王族暮らしが窮屈」とか「親しい友達がいなかった」などという凡庸な台詞のやり取りに終始する。永野芽郁の感情表現があまりに平坦なボイスアクトと相まってやり取りも耳に残らない。
このシーンに代表されるように、今作はキャラクターの内面や関係性がとにかく義務的で面白くない。2つの世界を舞台にしているという原作由来の特性を映画に持ち込んだはいいものの、映画というメディアに特に求められる人物造形やリアルタイムの会話といったものがどれも魅力に乏しく、ありきたりなのである。冒頭の現実世界のパートも本来なら登場人物同士の関係を書き込むべきなのに、仲良し3人組のうち内面が描写されたのは殆どユウのみという有様なので、コトナやハルの動向がどうなろうと正直関心が沸かないというのが本音だった。もっと彼らの日常を魅力的に描けていたなら、現実世界が立体的に感じられ、それと並行して存在する「二ノ国」にも興味が沸いただろうに。しかし、実際にはどちらの世界の描写も甘く、ただでさえありきたりな登場人物のドラマは全て台詞で説明するという工夫の無さなので、もう根本的にこの物語に興味を惹かれることがないまま、終幕した。
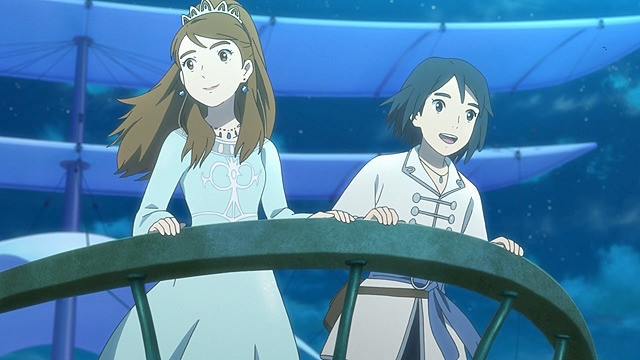
(C)2019 映画「二ノ国」製作委員会
全く共感できなくなっていく支離滅裂な登場人物たち
今作は、「台詞ですべてを説明しようとするつまらないドラマ」には留まらない。その上、稚拙な展開と人物描写のせいで、徹底して登場人物が理解不能な存在たらしめられる。
『二ノ国』山崎賢人のボイスアクトが素朴ながら等身大の高校生らしい息遣いが感じられてよかった。冒頭で友人たちに抱える劣等感を隠して気丈に振る舞おうとしてるのが言外で伝わって来た。それだけに話が進むにつれて、ユウはおろか、登場人物たちへの感情移入が極めて困難になっていくのが勿体ない。
— ワタリdley🕊 (@wataridley) August 24, 2019
今作で最も理解に苦しんだのが、W主人公うちの1人であるはずのハルである。自分はそのあまりの支離滅裂さ加減に、心の中で、といった類の喩えではなく、本当に鑑賞中頭を抱えて笑ってしまった。
彼は突如として送られた「二ノ国」について、街を歩く兵士を作り物ではないかと言っていたり、「町人AとB」と自己紹介したように、半信半疑の目を向けていた。そして脚が動くようになったユウなど理解を超えた出来事に対して「これは夢だ」と結論づける。だが、「二ノ国」のことを一旦は夢だと断定しておきながら、「目が覚めても夢からは覚めなかった」などと冷静なことを言ったり、ユウの「命の危険に晒されれば元の世界に戻れる」という確証のない仮説を信じて火に飛び込んだりもする。彼が自身の立たされた状況をどう捉えているのか、シーンごとにブレているから全く感情移入することが難しい。
帰還後の現実世界では「コトナが生きているから夢だったかどうかは関係ない」と唐突にあの非現実的な事象への興味を失くすのだが、コトナが余命幾ばくもないと知った途端に「アーシャを助けたからコトナは病気になった」などという飛躍した論を展開し始める。「アーシャの生存=コトナの死亡」に結びつける思考の過程が全く描かれていないし、そもそも「二ノ国は夢」という持論がこのシーンではすっ飛んでいて、前提として二ノ国が現実になっているのが意味不明である。このように、ハルの言動には一貫性が無さすぎて、ついていくことができない。激情してユウと口論していた次の瞬間には、冷静になりながら「二ノ国に来たのか」と事象を受け入れ、ワープしたトリガー(すなわち自分たちに降りかかった命の危機)に疑問を持つこともしない。これでは到底彼を生きた人間だと思うことができない。
親友の言うことを信じずにアーシャを殺すと宣った彼が、明らかに怪しいモンスターを飼っていて、明らかに怪しい素性のわからない男の言うことを聞き入れて、反旗軍の先陣を切って兵士たちを殺していく姿は、黒い鎧に身を包んでいるのとは無関係に不気味である。その最中にも「これは夢だ」という考えがぶり返しているし、いよいよ頭の中がどうなっているのかわからない。恋人を救うためとはいえ、親友に容赦なく斬りかかる精神性も含めて、元来彼は猟奇的な本性を持っていたのではないかという、おそらく作り手が望んでいないであろう見方ができてしまう。
しかも、散々戦争で幾多もの命が失われ、それが現実の火災事故に繋がっていることを知りながらも、一切の躊躇もなくその関心はコトナにしか向かわない。最終的に二ノ国が現実だったと認めるのはいいが、自分の過ちを反省したり、相応の報いを受ける描写もないので、ひたすら共感も教訓もないキャラクターとなってしまった。序盤、腹部にナイフが刺さった恋人を救急車ではなく自らの足で届けようとしていた時点で狂っているとは思ったが、まさかここまでとは思っていなかった。
全くリアリティを感じることのできない人物は、他にもいる。王は側近にあっさり騙された挙句、若者2人を闘技場で殺そうとする。生き延びたらそれはそれで反逆者呼ばわりし、理不尽極まりない強権的暴力をふるう。はっきり言って多大な過ちだと思うのだが、そのこと自体の反省もない上に、最終的に自国の兵を殺して戦争を煽ったハルも許すというこれまた不可解な言動を取る。
ユウと2人で湖のほとりで説明台詞をペラペラ語り、別れ際も説明台詞を語るアーシャは、もはやどうしてユウがそこまで肩入れするほどの人物なのかもわからない。守られるばかりのお姫様という立ち位置に甘んじており、意思が感じられない造形である。ユウが命をかけてでも守るということに説得力を持たせる努力の跡が見られず、時代遅れな上に退屈なキャラクターでしかなかった。

(C)2019 映画「二ノ国」製作委員会
相次ぐご都合主義、矛盾点
ここまで、今作の説明台詞自体がファンタジー世界の魅力を削いでいて、拙いが故に登場人物たちも肉付いているように見えないという問題を指摘してきた。
しかし、それらに留まらず、この説明台詞のオンパレードはご都合主義的な展開の権化にもなっている。
第一に今作の目玉である「命のルール」についてであるが、これらは全て台詞で説明された挙句に辻褄が合っていなかったり、詰めが甘い部分が散見される。
冒頭では側近のヨキが送り込んだ刺客は、明確にアーシャと命を共有したコトナの殺害を試み、結果としてユウとハルの2人は車に轢かれかけてトラベラーとなったわけであるが、どうしてコトナだけはトラベルしなかったのかは不明である。トラベルしなかったとして、そのままだと残った彼女だけは車に轢かれるか、出血多量で死んでしまうと思うのだが、この辺はバッサリと説明されない。ハルとユウが二ノ国を彷徨っていたのは戻ってきた時が日曜だったことからして現実世界と同じ時間の流れのようであるが、放置された彼女がユウがアーシャの腹部から剣を抜くまで生き延びれた理由もわからず仕舞いである。ついでに、あの刺客が隙だらけのコトナを放置して、終盤では二ノ国でヨキがアーシャを執拗に狙っていたロジックも謎だ。
それに加えて、二ノ国から帰還した際の描写も纏まりがない。最初の帰還後にはそもそもコトナが刺されたという事実そのものが改変されて無かったことにされているのだが、次の帰還後には癌そのものは改変されず快方に向かったという形で彼女は命拾いする。二ノ国にまつわる命の救済が、現実世界の事実を改変するものなのか、それとも自然な形で回復されていくものなのかが、バラバラなのだ。このあたりの作中ルールも甘く、ご都合主義感が非常に強い。ユウが消えた際に彼の関係者から記憶が消去されていく描写まで存在しており、一体どういう力が作用しているのだろうか。たぶん、脚本の力だ。
これらに関わる「命のルール」についての詰めの甘さは、ユウが「これは仮説だが」と語らせることで、巧妙に言い逃れしようとしているようにも思えて、なんだか釈然としない。そのユウが組み立てる仮説の数々も所詮は仮説に過ぎず、具体的な証明がなされるのは、ごく一部であり、今作は全体的に納得し難いものばかりになってしまっている。
最もそれが現れたシーンが、作中のクライマックスでお披露目されるミステリー風の種明かしパートだろう。ユウは側近であるヨキを、アーシャ殺害の主犯であり、反旗軍の首魁であると看破するのだが、その推理には一切の物証がない。「サキ姉をサキ姉と呼んだ」という薄弱な根拠(これより前に皆の前で「サキ姉」と口走っているため、ただの思い過ごしの可能性もある)から疑いを持ち、情勢不安と結びつけて宮廷内の関係者の仕業と断定し、彼の手から「魔法の匂いがしたから」という理由で犯人呼ばわりする場面は、もはや推理どうこう以前に、傍から見てただの言いがかりで笑ってしまった。
しかし、ただの憶測であるはずのそれについて、アーシャが援護し、「魔法には匂いがある」ことが判明し、その推理が正しいとされてしまう様子は、完全に脚本上の都合である。その後に続くヨキ=ガバラスの独白は、唐突な政治ドラマであり、脈略なく語られ出すので全く頭に入ってこない。知らない国の名前やちょっと仄めかされた程度の王族の過ちが簡素な静止画とひっきりなしの台詞で語られても、こっちとしては何の感慨もない。恐らくは劇中のあれやこれが全て繋がったという意図で書いたのかもしれないが、ただの後出しジャンケンにしかなっていない。
あと、どうやっても納得できないのが、「二ノ国では役が割り振られる」という仮説である。それに則して、闘技場では「俺たちは商人じゃなくそこそこできる戦士だったみたいだ」と言う。この映画の結末曰く、ユウとハルは同一人物が同時に存在しているわけで、片一方の世界からやってきた人物に役が振られるというのは正確ではない。更に元々二ノ国の住人で赤ん坊の頃より車椅子生活だったユウがどうしてあそこまで戦えるのかは不明である。ただのご都合主義で戦えるようにしただけなのではないだろうか。

(C)2019 映画「二ノ国」製作委員会
あまりに適当に済まされるユウのドラマ
今作はユウとハルのW主人公であり、自分が先ほど述べたように、異世界での冒険と対立を通じて2人が成長していくドラマとみなすことができた、はずだった。しかし、その成長劇も理解し難い形で締めくくられる。
そもそも今作はW主人公という体裁を取っていたとしても、冒頭のシーンから察するに、ユウが友人2人に対して抱えるコンプレックスの克服が「解決されるべき課題」として提示されていた。車椅子の彼が階段を登る事が出来ず、「邪魔者は帰りますよ」と言って去ってしまう出来事は、後に何かしらの形で解決された様子が映されると思うのが自然である。
ところが、今作はユウの車椅子という特徴そのものが、早々に意味のないものとして扱われるようになってしまう。二ノ国にトラベルしたユウはなぜか歩く事ができるようになり、その後も何らハンデを意識する事なく剣を振るったりもする。
車椅子生活だった彼にとって歩行できるようになったという変化は、その良し悪しを抜きにして、かなりの大ごとのはずなのだが、これが非常にあっさりしている。トラベル直後に、軽いノリで歩けるようになったことを喜んでおしまいである。自身の変化に気づかず、当たり前のように立って歩き始めたユウにしても、何でハルに指摘される前に驚かないんだと思ってしまう。
しかもその後には「俺が歩けるようになったようにコトナの怪我も治っているかもしれない」とユウに語らせている。アイデンティティが変わることに関して何の疑いもなく怪我が治るかのように捉え、それに頷くハルにも違和感を覚えて仕方ない。
そうしてもはや車椅子であることは何ら意味を持たなくなり、コトナとハルに対するコンプレックスもいつの間にやら消えて無くなっている。2回目の帰還後には、ヨキが送り込んだ刺客から逃げる際にも、怯んでいる隙に車に乗りこむ描写があるが、いくらなんでも無理があり過ぎて、車椅子の彼を車に乗せる隙をあの刺客がわざわざ与えてくれたとしか思えない。序盤にも車椅子のユウをコトナが助けに呼び出す描写は違和感が半端なかったが、とにかく全体を通して、「車椅子であること」を軽視した描写が散見される。
結局、ユウは元より二ノ国の住人で歩行できる体のまま留まる結末を迎えるが、車椅子に乗らなくなるロジックが欠けており、成長したようには映らない。せいぜいすでにボーイフレンドのいるコトナではなく、自分と意気投合したアーシャと添い遂げるぐらいの話であり、身体の変化は何ら意味を持っていないのだ。今作はなまじデリケートなアイデンティティの問題を扱い、とても不誠実な形でそれを終わらせてしまっている。
単に脚本が拙いというのも頷けるが、そもそも車椅子の人が歩けるようになるという変化を描いた意図が軽薄で、これでは批判されても仕方ないと思う。日本ではアニメーションのみならず、全体的に障害を抱えた人々がフィクションに登場しないという点に自分も大きな違和感を持っている。そうした風潮に対して少しは挑もうという気持ちがあるのかもしれないと期待したが、描かれたのは「アイデンティティの肯定」という結末ではなく、「アイデンティティの放棄」を劇中であっさりと流した末の強引すぎるオチでしかなかった。
ユウ=ハルという結末は、「同じものを好きになる」という根拠で結論づけられているが、いくらなんでも強引すぎて、頭が追いつかない。というのも、そもそもその同一の趣向性というサンプルがコトナ=アーシャしか示されておらず、ユウとハルはコトナを好きであるという点を除いて性格も外見も全く異なるように描写されていたからだ。酒場のポールダンスや医師団のダンスに尺を割くぐらいだったら、この結末に向けた伏線を張るぐらいしてもよかったのではないかと思う。その方が、いきなり後半の回想シーンで強引に「俺たち似てるよな」と語らせまくったりするよりも、はるかに素直な驚きになったはずである。

(C)2019 映画「二ノ国」製作委員会
まとめ: ゲームの設定はそのまま映画にするものじゃない
プレイヤーが数十時間もエンゲージすることになるゲームを原作としているとあって、100分程度にまとめるというのは、それだけでも無理難題だったことは想像に難くない。『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』はそうしたゲームの映画化を考慮した筋書きになっていたが、こちらの作品はゲームの設定をそのまま映画に落とし込んだような雑さが随所に表れていて、かなり歪な形になってしまっている。
自分は原作のゲームをプレイしたことはなく、プレイ動画などを見て「ジブリの絵柄をそのまま動かせる」という点が強みなのだなと思っていた。今作は実際にジブリで働いていた百瀬義行が監督を務めていることとゲームに忠実とあって、ジブリ的ファンタジーを期待させる外見に仕上がっている。だが、逆に言うと魅力はそれだけで、その他の部分はお世辞にもジブリのファンタジー作品に遠く及ばない。ゲームの独自の設定である「一ノ国」と「二ノ国」の往来とその法則を説明することに終始した結果なのか、映画らしい映像表現のチャレンジや限られた時間で登場人物に寄り添いたくなる人物描写は一切見当たらなかった。戦争の場面では、明らかに作画から3DCGが浮いているなど、作業の適当さが透けて見えた。
日野晃博氏の描く脚本とは相当相性が悪いのか、兎角作中の倫理観や工夫のない説明台詞、既往の創作物で何度も目にした設定の数々などが、肌に合わない。映画を傍観したまま過ごす2時間近くというのは、こんなにも過酷なものかと久々に実感した次第である。
関連記事: 異世界ファンタジーのアニメーション映画作品
▼同じくワーナー・ブラザース配給で、あの原恵一監督が送る異世界「旅行」譚『バースデー・ワンダーランド』
▼錬金術が発達した世界と科学技術が発達した現実世界を軸に社会への関心を描いたハガレン『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』
▼同じくRPGを原作としながらも、映画化にあたってのアプローチが異なる『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』

















[…] ワタリドリの手帖 ゲームの設定をそのまんま映画の脚本にしたらこうなる… アニメ映画 シェアする Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー kuchi クチコミジャパン […]