1989年に連載開始以降今も絶大な人気を誇るダークファンタジー漫画『ベルセルク』(原作・三浦建太郎)を、『ポケットモンスター』を放送する傍らで、1997年にOLMが制作したのがこの『剣風伝奇ベルセルク』。
高橋ナオヒト監督をはじめ、美術監督の小林七郎、総作画監督の千羽由利子らアニメーターの面々など、のちの『ToHeart』『鋼鉄天使くるみ』『フィギュア17 つばさ&ヒカル』にも名を連ねているスタッフが多数参加している。全編に渡って緻密な画面レイアウト、淡い色が静かに目を引く美術や時折挿入されるハーモニー処理のカット、引き算的な演出の中で浮き彫りになるキャラクターの丁寧な表情や芝居など、それらの作品と通ずる拘りが変わらず見て取れる。
それらについて語るまでもなく素晴らしいのは前提とした上で、本作について語ろうとすると真っ先に触れたくなるのが、「蝕」という容赦のない結末への道行に絞った物語の構成だ。
本作は原作漫画3〜14巻の「黄金時代篇」を中心にした構成を取る。本来『ベルセルク』は、第1話で描かれたように、黒い剣士を名乗り人を襲う異形の怪物・使徒を退治して回る主人公ガッツの冒険から始まる作品である。一方でこの『剣風伝奇〜』は1話と最終回のエピローグを除いて、本編の殆どを過去編が占めている。
この割り切った構成になっている事情としては、本作がアニメ化された時点では『ベルセルク』は黄金時代篇の後は原作のストックが十分でなかったことが考えられる(もっと言うと、アニメ化が企画され出した段階では黄金時代篇真っ只中だろう)。それでもガッツの黒い剣士としての動向を原作漫画をベースにオリジナルも交え、そこに一塊の過去の回想シーンとして黄金時代篇を挿入するという構成も取り得る案の一つとして検討されたのではないかと想像されるのだが、本作はその真逆に贅肉をこそぎ落としてガッツが鷹の団でグリフィスらと過ごした青春時代をこの作品の核として定める方法を採った。
原作漫画では1話の時点で登場していたエルフ(本作では指輪物語のイメージのような亜人種ではなく妖精のような姿である)のパックをはじめ、黄金時代篇の途中にも出てくる強いインパクトを残すキャラクター(バーキラカ、ワイアルド等)、その他本筋を描く上で周辺的な部分(ミッドランド貴族内のサブエピソード)は尽くオミットされ、ガッツ、キャスカ、グリフィスの3人の心の漸近とすれ違いを見せ切ることを最優先とした映像化になっている。結果、原作漫画において衝撃的な展開として今も語種となっている「蝕」は、より鮮烈な決壊として、そこへ至る不穏さと映像的なインパクトを大きく増している。
1話や6話でこそヘビの使徒とゾッドら異形の存在は登場するし、ベヘリットなる不穏なアイテムは出てくるのだが、基本的には戦において携帯式の銃火器は見られず専ら剣や槍や弓矢で戦う中世に極めて近い文明下の、戦や権力争いを背にした骨太な大河ドラマの様相で物語は進んでいく。グリフィスにその実力を見込まれながら、自らも彼の立てる戦略に身を預けるガッツが大剣を振るっては武勲を上げていくという骨太な戦記物であり、原作では導入の3巻までがそもそもダークファンタジーであったことから隠す気配もなく異様な存在が出てくるものの、『剣風伝奇〜』においてファンタジー的な事象は道中匂わせる程度に抑えられている。
そうした取捨選択は演出面にも作用しており、ベルセルクに欠かせないコメディリリーフのパックに代表される漫画の表現は鳴りを潜め、驚くほどに茶化しが入らない。本編の大半はガッツ、グリフィス、キャスカの3人を中心とした質実な人間ドラマが展開され、彼らの心の有り様は高い作画技術でしかなし得ない繊細でリアルな表情で視聴者にその内実を感じ取らせるストイックな志向。平沢進が担当する劇伴音楽も印象的な本作だが、1話ではそのBGMはクライマックスになってようやくかかるというほどに本編は装飾を盛る足し算的な演出よりも、静かなタッチの中で着実にドラマが積み上げられていく。
出会った当初はただ戦場を生き延びていくばかりの日々を過ごしていたガッツ。そんなガッツに惚れ込み彼を鷹の団へ引き入れ、着実に夢路を歩んでいくグリフィス。そして、グリフィスに対する慕情、ガッツに対する嫉妬の狭間で揺れるキャスカ。戦場を駆け抜けるにつれて彼らの関係が信頼で結ばれていくのも束の間、グリフィスの底知れない野心を垣間見たことを発端に、只管生きるためだけに剣を持ち続けてきたガッツに迷いが生じ、その果ての決断がキャスカ、グリフィスらとのすれ違いを生む人間模様。その先に、因果に誘われるがまま、大いなる破局「蝕」を迎えてしまうという、人の世の不条理を見るような残酷な結末。
その惨禍が頂点に達したところで、視聴者を放り出すように幕を引く。誰の目にも、中途半端なオチだと指差しされることは分かる幕引きである。実際、蝕にはまだ続きがあり、脱出後にも生き延びた者同士の再会やガッツの黒い剣士としての門出が描かれるのだから、映像化もそこまで収めて然るべきというのも頷ける。ここにおいて重要な役目を持っていた髑髏の騎士は存在ごと根こそぎカットされている本作において、ガッツがどのようにあの状況から生き延びたのかははっきりと謎であるし、リッケルトとキャスカの生死も不明のままとあって、これらの答えは原作を頼っていると言わざるを得ない。
しかし、この作品においてある意味それらは重要ではないという見方もできる。要は、ガッツがなぜ1話のようにグリフィスなる存在に激しい憎悪を向けて物騒な二つ名を喧伝しては使徒を狩っているのかというその一点に繋げるのであれば、極端な話ではガッツとキャスカがあの後どうして蝕を抜け出したのかすらも問題外なのだ。この『剣風伝奇〜』は必要最低限を描いて終わったとも言えるし、視聴者が抱いた主たる疑問の数々は原作に手を出せば分かるようになっているという点では、原作漫画への強烈な手引きとも言えるだろう。
何よりもこの放り出されたような呆気に取られた感覚は、全25話の一つのアニメーション作品だから成し得た境地に感じられる。原作における転換点の「蝕」を一級の作画と演出で物語の最後に置いた本作は、『ベルセルク』という原作の再現を志す代わりに、自らの意思を通じ合わせることができずに残酷な破局に向かってしまう宿痾とも映る人間の因果を追わせ、その果てにある「蝕」へ見る者を引き摺り込むことを選び取っている。後にも先にも、これほど振り切った作品は、原作の再現が至高とされる昨今において、なおのこと見ることは叶わないのかもしれないと思うのだった。



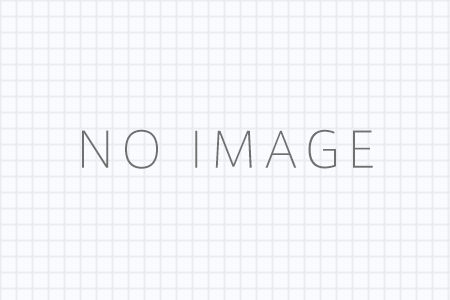

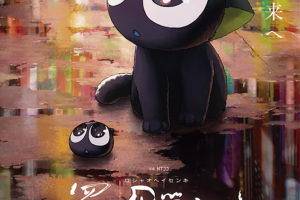








コメントを残す